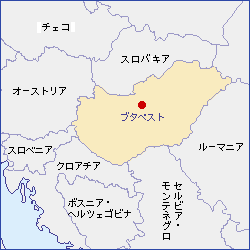○はじめに
久しぶりの世界史レポートにして、久しぶりに登場の八十八舞太郎がお送りします世界史レポート。
今回はちょっと、こわ〜〜い話です。そういうのが苦手な人は、あんまり見ないことをお勧めします。ふっふっふ。
○美しく老いることは 至難の業だ by アンドレ・ジイド
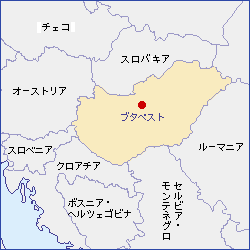
分かりきったことではありますが、全ての生きるものは老い、そして滅びていく存在です。しかし、人はその事実を知り、それに抗うエネルギーを持っています。とりわけ「老い」に逆らう…若々しさ、美しさを保つために、日々様々な化粧品の宣伝が飛び交い、肌年齢を保つ食品やサプリメントといった美容に効果のあるかもしれないものが店に堆く(うずたか−く)積まれ、人々が先を争って買い漁る時代です。
16世紀末〜17世紀初頭のハンガリーにも、そんな我々と変わらず若さと美しさを保ちたい、と思っている一人の伯爵夫人が居ました。名前は「エリザベート・バートリ」と言います。しかし、この女性がたった一つだけ違っていたのは、その美しさを維持するために「人の生き血」を用いた、ということです。
*この時期は、日本では安土桃山時代・江戸時代、中国では明の時代末期になりますね。
*地図は外務省ホームページより
○そもそも、エリザベート・バートリとは何者?
今回紹介するエリザベート・バートリとは何者なのでしょうか?
彼女が生まれたバートリ家というのは、ハンガリー国内でも1、2を争うほどの名家でした。しかし、その家系には性的倒錯者や精神に異常を持っている者が多く、頭のネジが5、6本外れた人が殆どだったそうです(家の財産と領地を分割しないために近親婚を重ねていった結果、このような結果になったらしいのですが)。…おお、仲間かも。
1560年に生まれたエリザベートは、14歳の時にやはり国内でも指折りの名家、ナダスディ家のフェレンツと結婚します。エリザベートが若い頃の記録は殆ど残っていませんが、異常な性癖はこの頃からちらほらと見受けられるようになってきます。ある時、粗相を犯した召使の少女を、衣服を剥いで身動きできぬよう木に縛りつけた上、全身に蜂蜜を塗りたくって一日中放置し、蜂や蟻に噛ませたという話が残っています。
夫フェレンツとの間では子どもに恵まれず、そのことでイライラしていた(後に4人の子どもが生まれますが)彼女は、妖術的なものにも関心を示し、それに傾倒していきました。それが後の『血塗れの伯爵夫人』とまで呼ばれる原因となった所業の数々の要因の一つとなったのかもしれません。
○血塗れの伯爵夫人
『それ』はある日突然やってきました。
いつものように些細なことで腹を立てたエリザベートは、召使を鼻血が出るほど強く叩いてしまいます。そして手に付いた血痕を拭ってみると、その箇所がやけにみずみずしく感じました(確かに自分の感覚としても、血の付いた箇所を拭うと妙に滑々しているとは思うのですが)。既に美しさを維持することに半ば強迫的になっていた彼女の、後の世に語り継がれる血の惨劇はここから始まります。
それからしばらくして、彼女が44歳の時に夫が亡くなってしまい、それを期に彼女の行動はますますエスカレートしていくことになります。彼女が住むチェイテ城下の村の娘たちを召使にする、という建前の元に集め、その後数年間に渡って拷問は行われました。彼女のお気に入りの下男フィッコ、子どもの乳母として雇い入れたヨー・イローナ、その助手ドルコも加えて実行された大虐殺の犠牲になった女性は、約600人に上ると言われています。
その代表的な手段を少し並べておきます(注・以下の文は非常に残虐な描写が一部含まれるため、そういった話が苦手な人や、想像力が豊かでその様子がありありと脳裏に描かれるような人は、なるべく避けるようにした方が良いかもしれません)。
※鋼鉄の処女
「アイアン・メイデン」と呼んだ方が分かる人もいるのではないでしょうか。元々は中世に作られた拷問器具です。人より一回り大きい、中が空洞になった鉄製のからくり人形で、胴体内部には五本の刃が仕込んであり、人を閉じ込めて扉を閉じると、針が体中を刺し貫き、切り裂き、砕き、血を絞り取る。流れ出た血は、アイアンメイデンにある溝を伝って回収され、エリザベートの肌を潤す、という寸法です。この機械人形、実際の人のようにからくりによって眼を開くし、人間のものである歯や髪の毛もあったそうです。
ちなみに日本では明治大学刑事博物館でギロチンなどと共に展示されています(複製品ですけど)。
デジタルミュージアムで見られますので、こちら からどうぞ。
※鉄の鳥籠
「鋼鉄の処女」と並んで有名な拷問器具です。
人一人が犬のように屈んで入れるくらいの鉄製の籠で、人を入れて上空に吊るし上げた後、両側から棘付きの壁が迫る。両側に棘が付いているので、右に逃げようとすれば左の棘に突き刺され、逆に逃げようとすれば逆側で刺され、そもそも不安定な空中ゆえ動くたびに振り子のように鳥籠が揺れてしまう為次々とその棘に刻まれてしまう。そして肉片と化すまで血を絞り取られてしまう、という凄まじいものです。流れ出た血はそのまま下へと滴り落ち、彼女の美貌の糧となります。
※血の饗宴
年月が経つごとに、夜毎行われる拷問のため死体の処理が追いつかず、その腐敗臭が城下に漂い、また夜になると城の地下から悲鳴が上がったりすることから城下の住民の噂となり、地元の住民が召使として雇えなくなりました。そのため今度は付近の貴族の娘を集めて拷問を行うことになります。
しかし、結局貴族の娘もすぐに足りなくなってしまったので、従者は近くの農家の娘を拉致同然で連れて帰って「貴族の娘」と偽り城に監禁していました。そうして貴族として集められた娘の内60人は、「宴会」に招かれたテーブルで全員が首を落とされました。その様はまさに『血の饗宴』と呼べるべきものです。
因みに、殺してしまった後で血を抜き取っても、腐敗が始まってしまっているので、これらの拷問器具は血を絞れるだけ絞り取るギリギリまで生かしておくように設計されていました。拷問にかけられた娘たちが、激痛、苦悶のあまり叫び声を上げながら絶命していく様もエリザベートは愉しんでいたということです。
この他、なお、他の拷問の手段として
・焼き小手を口の中にねじ込む
・ピンで全身を突き刺す
・服を剥ぎ、凍った湖の水をかけて氷の像に仕立てる などもやったそうです。恐ろしや。
○そして・・・
やがてこの大虐殺の事実は、世間の目に晒されることになります。
一つは、血を抜かれて殺された女性を埋葬する際にたびたび居合わせた神父が、あまりにもその回数が多いことと、その死体の状態があまりにも異様であること(全身が細かく刻まれていたり、死体が篩のように穴だらけだったり)に疑念を持ち、教会の教区監督にそれを通告したこと。
また、農民の一人が、彼女の息子の後見人で政敵でもある人物に面会をし、自分の知り合いが帰ってこないことと、城下に広まっている「女吸血鬼」の噂を訴え、それが国の議会に上告されたことなどから、1611年に裁判にかけられることになります。
この裁判は当人のエリザベートは出席せず、共に拷問に加わったフィッコ、ヨー、ドルコなどが被告として出廷しました(この裁判記録は今でも存在しています)。裁判でこの三人は死刑が確定し、即日執行されました。なお、この裁判に宗教が絡むことはありませんでした。もしこれが宗教裁判となると、エリザベートは「魔女」とみなされ確実に火刑台に上がることになるため、裁判を担当した裁判官が、後述の「面子」に配慮したものであるそうです。
それ故裁判は迅速に進み、裁判当日に死刑執行という異例のスピードで決着がつくこととなります。
一方、主犯格?のエリザベートは、バートリ家がハンガリー国内でも最高の名門の一族であることから、その面子のことも考えられ最終的に終身刑を宣告され、余生を居城チェイテの、明かり取りの小さな窓と一日一回の食事を差し入れるための覗き窓以外は厚く塗り固められた自室で、一切の面会も許されずに過ごすこととなります。
それから3年半が経った1614年8月21日、54歳でエリザベート・バートリはこの世を去りました。
○そして・・・
永遠の美貌を手に入れるため、600人にも及ぶ女性を拷問にかけ、その血を求めたエリザベート・バートリは、ルーマニアの「串刺し公」ヴラド・ツェペシュと並び「吸血鬼」の二大モデルとされています。そもそも「吸血鬼伝説」というものは古くから存在し、この二人がそのイメージに合致したため、モデルとして出来上がってしまったのが事実のようです。
現地では彼女が亡くなった後も血を抜き取られた女性の変死体が見つかり、「エリザベートの仕業」と恐れられたという言い伝えも残っているそうです。後年作られた小説の中の女吸血鬼「カーミラ」は、彼女をモデルにしたといわれています。
ヴラド・ツェペシュとエリザベート・バートリ。
共に吸血鬼へと仕立て上げられた2人ですが、この二人を隔てる大きな『壁』があるとするなら、その「目的」ではないでしょうか。確かに「串刺し公」と揶揄されるまでの行為(敵国の戦意を削ぐため、生きた捕虜を杭にぶっ刺して並べ立てていたという話を聞いたことがあります)をヴラド公はしていますが、あくまでもそれは「政治的な」行為であり、もしかしたら本人の意にそぐわない行為だったかもしれません。
しかし、エリザベート・バートリは純粋に自らの「欲望」のために若い女性たちを集め、殺し、その血を集めました。彼女はまさに「生きるために」それを行ったのです。彼女から「血」を取り除いたら何が残ったのでしょうか(本当に血を抜くという意味ではなく)。自らが生きるため、純粋に血「そのもの」を求めたエリザベートは、その意味でヴラド公よりも吸血鬼「らしい」人物に感じられます。
ざっと彼女に関する事柄を掻い摘んで説明してきましたが、さて、ここに記されていることは、「吸血鬼」と呼ばれる人智を越えた存在による行為なのでしょうか?…いえ、これらは、我々と同じ「人間」が行なった事実です。彼女も今の人たちと同様に、自らの美貌が維持されることを望んできました。しかし、それはあまりにも「完全」を求めるが故、後世「女吸血鬼」と呼ばれるような行為へと至ってしまったのです。
後世にまで語り継がれる「女吸血鬼」エリザベート・バートリ。永遠の美を望み、血を求め続けた彼女は、人が本質として持つ、欲望を求めるときの、「完璧」であることを望むときの残酷さ、というものを体現していたのかもしれません。
確かに、人間としてのエリザベート・バートリは、1614年にこの世を去りました。しかし、「吸血鬼」としての彼女は、400年近く経った今でも、鏡の中に、その鏡を覗き込んでいる私たちの中に存在しているのかも知れません。
参考文献
「血の伯爵夫人−エリザベート・バートリ」 著・桐生操
1995・新書館
※この本の巻末には、付録として、エリザベートから遡ること約130年前、彼女と同じように同性愛、虐殺に奔った、「青髭公」のモデルとされているジル・ド・レ公爵の話が載せてあります。この人物はジャンヌ・ダルクと共に戦ったあとに、危ない方向に道を踏み外してしまった人物で・・・。現代の猟奇的犯罪に繋がる部分も所々にあり、非常に興味深いので、関心がある人は紐解いてみると良いかもしれません。
↑ PAGE TOP
data/titleeu.gif
| | | | | | | | |