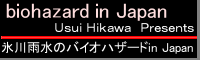第10話:ホストコンピュータ
「ホストコンピュータ、ねぇ…。今時、こんなタイプのLANもあるんだな。」ホストコンピュータが起動していないと、他の端末は役立たず、とはずいぶん不便なシステムに思える。まぁ、本来は常に起動した状態なのだろうが…。しかし、別に今すぐ起動しなければならないものでもあるまい。最優先事項は連中を見つけ、安全に脱出する事。その過程で機会があれば、という程度でいいだろう。第一、何処にあるのかも判らない。
事務室を出たあと、手塚は診察室巡りをしていた。
妙にリアルな人体模型のある外科や、普段は子供を安心させるぬいぐるみが、なぜか動き出しそうな気がして不気味な(実際、何かの偶然だろうが、壁に掛けられていたくまのぬいぐるみが落ちてきたときは、思わず身構えてしまった)小児科には特に異常な点は見当たらない。
もちろん、机や戸棚に残されていた資料や患者のカルテにも目を通すが、彼が見た限り不審な点はない。
さらに、皮膚科にまわって捜索を続ける。1体だけゾンビがいたが、何のことはない。落ち着いて頭に2発ほど打ち込めば、倒れて起き上がらなくなった。そして、例によりカルテのチェック。受付で見た診察記録の通り、ここ1週間のものが多い。その症状の多くは腹部、大腿部、及び粘膜に痒みを伴う炎症、下半身を中心として現れる紫色の斑紋、など。やはり、日付が若くなるほどその症状は悪化していることが見て取れる。
しかも、それらの言葉の横には必ずといっていいほど「UNKNOWN(不明)」の文字が添えられていた。
だが、病院側としても、原因不明のまま放っておくわけにも行かなかったらしく、いくつかのカルテには血液検査や尿検査の結果が貼付されていた。20近い項目が並び、個人では正常値を逸脱した数値もあるが、どうやら持病によるものらしく、全員が共通して高いのは、残念ながら白血球の値くらいだ。これでは何も分からない。
そんな平凡な数字の羅列よりも、彼の興味を引いたのは一番下の空欄に記された一行の走り書きだった。
「血液中に未知のウィルス抗体を検出。病原性の疑いアリ。要、培養試験。」…。
これでほぼ、はっきりした。この町の住人のゾンビ化は、何らかのウィルスが、何らかの理由で、何らかの経路を辿り伝染した感染症に過ぎない。ならば、相手は怪物ではなく、単なる病人なのだ。必要以上に恐れることはない。
…しかし、その病人を撃ち殺した俺は…、人殺しか?
未知の怪物に対する、どこか非現実的な恐怖感は消えたが、今度は人を撃ったことに対する、現実の呵責が心に枷をする。ついさっき、降りかかる火の粉を払うように撃ち殺したそのヒトを見て、心が自らに問う。
「オレハ、モウイチド、ヒトヲ、ウテルノカ?」
そんな声を意志の力で押し潰しつつ、しかし、拳銃を握る右手に、かすかな震えと不安を抱きながら彼はその部屋を後にした。
内科、神経科、その他残りの診察室を見て周り、カルテを始めとする資料に目を通したが、その内容は皮膚科のものとそう変わらず、「原因不明」の文字が踊っていた。
しかし、一応、総合病院ということもあって、各科間での連携があったことも見て取れる。その点でもカルテが画一的になるのは当然だろう。それでも、同じことが、まるで判を押したように書かれていることはやや不自然だが、気にしても仕方がなさそうだ。次は薬剤部にでも行ってみよう。何か役に立つ薬があるかもしれない。
これでも一応、薬学は専門分野だ。未熟ながらも役に立つ知識もあるだろう。ある程度、何がどの薬かはわかるつもりだ。これからのことを考えると、止血剤、鎮痛剤、アンモニアなどの刺激物(気付け薬になるだろう)などがあると助かる。出来れば、覚醒剤があればベストなのだがそこまでは期待しないし、なるべくなら使いたくない。他にも硫酸や各種のアルコールなど、適当な薬品があれば、武器やトラップが作れるかもしれない。
様々な期待を胸にノブを回すが、ドアは全く動かなかった。反射的に無駄だと分かりつつも2,3度、ガチャガチャと押し引きする。…やはり動かない。…カギだ。考えてみれば当然だった。薬剤の保管室は病院において、素人を最も入れてはいけない場所のひとつだ。そんな部屋を施錠しない道理はない。ならば、何処かでカギを探さなければならない。今まで見た部屋ではそれらしいものはなかった。
となれば、現状で最も可能性が高いのは警備室だ。
警備室のドアをあけると右手に机、奥の壁には黒板とロッカー、その横にはいくつかカギが掛けてある。机に伏している警備員を含めた、その配置は夕方の交番を思い出させる。もう遠い昔のようだ。
いまだ目を覚まさない警備員のゾンビを刺激しないように注意しながら、奥まで足を忍ばせカギを見る。それぞれ、部屋の名前が書かれたプレートの下に対応したらしいカギが掛けられているが、その中に「薬剤部」の文字はない。
おそらく、管理責任が全て顧問薬剤師に一任されているからだろう。だが、収穫が全く無いわけでもなかった。薬剤部以外には地下にあった「機械室」や「ポンプ室」のものをはじめ、いくつかの部屋のカギがある。手塚はそれらを普段から持ち歩いているキーホルダーにまとめ、ポケットに押し込んだ。これでほぼ全ての部屋に入ることができるだろう。
その後、黒板とロッカーを調べるが、勤務予定が書かれていたり、警備員の私物らしいものが納められているだけで特に見るべきものはなかった。これ以上、そんなものを見ていても何も出て来そうにないので、さっさと出て行くことにする。幸運にも警備員の死体は死体のままでいてくれた。
その足で救急搬送口と緊急措置室にも行ってみたが、そこから出られるわけでも、何かあるわけでも、まして、誰かいるわけでもなかった。これで一通り、1階は見てまわったことになる。いくつか情報はあったが、肝心の友人連中は見つからない。となれば、次は2階に行かなければなるまい。
エレベーターが作動しないので、階段で2階へ向かう。地下や1階でもそうだったが、所々通電していない場所があるらしい。そういえば、皆川はどうしただろう。こちらはいろいろ時間を費やすことも多かったので、そろそろ鉢合わせてもいいような気がするのだが…。まぁ、自分と同じで何かあったのかも知れない。どちらにしろ、単純計算ならば一人2,5階ずつまわって、2階の中ほどで落ち合うはずだ。
2階は全体が主に内科の入院施設になっている。かなりの数の病室があるので、一部屋ずつ見ていてはかなり時間がかかりそうだ。そこで手塚は、とりあえず階段を昇ってすぐそばにあるナースステーションから調べることにした。しかし、近寄ってみると中から電子音が聞こえる。昔のポケベルか、携帯電話の呼び出し音に近い。…誰か、いるのだろうか…。しばらく経っても鳴り止まないその音は、彼の緊張感を掻き立てる。手塚は注意深くドアをあけた。
真っ暗な部屋の中にデジタル時計や、何かの機械のスイッチランプが闇に浮かぶ。その中でひときわ大きく点滅する赤い光が奥の壁にあった。先ほどの正体不明の音とシンクロする点滅。どこか焦燥感をあおる電子音。似たような電球が縦に並び、その隣には3桁の数字と人名。以上の状況証拠から導き出される応えは一つ。誰かがナースコールをしている。即ち、誰か生存者がいて、それを外部に知らせようとしている!部屋番号は230号室。入院患者のいない空き部屋らしい。ならば、さらに彼らである可能性が高い。手塚はすぐにナースステーションを飛び出し、廊下を走り出した。
途中、何体かゾンビが現れたが関係ない。バスケットやサッカーの要領で、ごく簡単なフェイントを掛ければ簡単に回避できるし、加速をつけた跳び蹴りや当身でも十分対応できた。徐々にその部屋が近づいてくる。
223…、225…、226…、
227…、228…、
230。…ここだ。
ドアをあけると、まず目が眩んだ。廊下はかなり薄暗いのに、その部屋には煌々と明かりが灯っていたからだ。本来、それが当たり前なのだろうが、夜の闇によって拡張された彼の瞳孔にその光量は多すぎた。
数秒後、少し慣れた目で、中を見渡す。かなり広いがベッドは一つしかない。ややランクの高い個室のようだ。しかし…、誰もいない?不思議に思って一歩中に踏み込んだ瞬間、ドアの陰に隠れていた何かが飛び掛ってきた。
「ガンッ!!」
最初に感じたのは側頭部への衝撃。眼前に閃光が走り、その一瞬後には真っ暗になった。次に左半身で感じた硬質な感触によって、自分が床に倒れたことを知る。そして染み渡る激痛。しかしそれも遠のく意識と共に薄らいでゆく。入れ替わりに襲うのは恐怖。必死で床を掻いて間合いを取ろうとするが、もう力が入らない。
…ダメだ、ここで、意識を、失ったら…、やら、れ、る…。
そして、最後に聞いたのは主の分からない人の声。
「止めろ!よく見ろ!ソイツは…」
やめ、ろ?なに、を?よく、みる?もう、みえないんだよ…。なにも…。