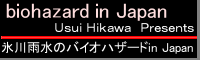第14話:途切れた日記
心の中の靄と苛立ちを少しでも振り払おうと、ドアを乱暴に開けて廊下に出る。響く音が空しい…。2階の部屋はもはや調べ尽くしたので3階へ上がってみることにした。2階が内科病棟であったことに対し、3階は二つのブロックに分けられている。一方は病室や手術室のある外科病棟、他方は会議室や院長室がある一般人は入ることが許可されていないブロックだ。
病室を巡り、中を見ると狭間が言ったとおり、死体がベッドに寝かせれている部屋がある。
「流石に寝起きでコレはきついよな…。」
死体のいくつかはゾンビとして復活したものもあるようだった。だとすれば狭間たちは目覚めと同時にゾンビに喰われる可能性もあったということだ。そうならなかったことは幸運といわざるを得ないだろう。そんな部屋の一つに入る前、ドアの横の病室名簿に見慣れた名前を見つけた。
「牛田明俊」…。
皆川から、この病院に入院していることは聞いていたが、いざ現実を突きつけられると、動揺する。この扉の向こう側には彼の死体があるかもしれない。いや、死体ならばまだ良い。ゾンビになっていれば、この手で安息を与えねばなるまい。自分の身を守るためにも、そして彼のためにも…。
手塚は一つ深呼吸をして、銃を構え、そして注意深くドアを押した。
もぬけの殻。そう表現するのが妥当だろう。ベッドやキャビネットなどの備品以外には人っ子一人、ネズミの子一匹いない。だが、彼が使っていたと思われるキャビネットからは、1冊のノートが見つかった。どうやら彼が日記をつけるのに利用していたらしい。
「他人の日記を勝手に見る趣味はないのだがな…。」
しかし、現状で彼に対する手掛かりはこのノートに頼るほか無いだろう。
6月29日
「主治医にリハビリテーションの一環として、日記を書くことを勧められた。右腕は派手に骨折していたものの、きれいに折れていたらしく、リハビリ次第では後遺症は残らないそうだ。自覚はないがむしろ足のほうが重症らしい。しかし、今はたったこれだけの文字を書くのにも、1時間近く掛かってしまう。文字自体もほとんど読めないほど汚くなってしまっている。全く、明日からのリハビリが思いやられること、この上ない。」
7月18日
「最近、病院全体が妙にあわただしい。特に根拠はないのだが、なんとなくそんな気がする…。その上、今日、突然自分の主治医が交代になった。入院治療中に主治医が代わるなど、聞いたことが無い。新しい主治医は冷たく神経質そうな印象で、医者というよりも何かの研究者のようだ。話では、病院側、というより前任の主治医の『止むに止まれぬ』事情があったらしいが…。おかげで落ち着いてリハビリも出来ない。こんな状況では、治る怪我も治らないし、むしろ病気にでもなってしまいそうだ。」
7月30日
「昨日は鹿尾町において夏ではほとんど唯一の祭事である「白神祭」だった。冬は冬で花火大会があるのだが今は関係ない(ちなみに今年は12月22日開催らしい)。娯楽の少ない町なので楽しみにしていたのだが、こんなことになってしまい残念だ。この祭りの見せ場は青年団による山車なのだが、見舞いに来た家族の話では、今年はその山車からスモークだかミストだかを撒き散らしたらしい。町も無駄なことに金をかけるものだ。」
8月2日
「今日、主治医から引越しを告げられた。と、言っても要は個室に移るだけなのだが…。話では退院も近いのでより良い環境で最終調整をしたい、ということだが、自分はこの4人部屋のほうが性に合っているのに、何故、半ば強制的に、そんなおせっかいを焼かれるのだろう?しかし、「退院が近い」と言われたのは嬉しかった。いくら4人部屋が性に合っているとはいえ、病院自体あまり好きではない。1日でも速く退院したいものだ。」
日記はそこで終わっていた。
しかし、既にこの病院の個室は全て見たはずだ。それでも、彼の手掛かりは全く無かった。それどころか、ここには彼の身の回りのものと思われる品が一式残されている。まるで、彼だけが消えたように、あるいは、連れ去られたように…。しかも、2週間近くも居なくなった人間の荷物をそのまま置いておくはずはない。一体、何故…。しばらく考えてみたものの、何も分からないということが分かっただけだった。
だが、いつまでも彼のことを考えているほど余裕はない。手塚は再び薄暗い廊下を走り出した。そして、こちら側のブロックでは最後に残った手術室に入る。本来は前室で徹底的に手洗い、消毒の上、手術着に着替えなければならないのだが、本来の目的で入るわけではないので省略。どこかタブーを破る快感がある。
手術台には解剖途中のゾンビが寝ていることくらいは覚悟(若しくは期待)していたのだが、手術室全体において不審な点はない。
しかし、彼が手術室に来たのには捜索以外に、もうひとつ目的があった。そろそろ弾薬が残り少ない。以前は手術器具の武器としての使用を諦めたが、もはや背に腹は代えられない。数ある手術器具のうち、武器として使えるもの…。彼が選んだのはメスだった。意外と知られていないが、メスは日本刀に匹敵する切れ味と同等に破壊力も高い。使い方によっては骨すらも切断することが可能だ。
加えて、手塚は医学部に紛れ込んで参加した人体解剖実習の際、教官に「メスの使い方だけはプロ以上」と評価されたことに対する自信があった。正確に狙えばメスのような刃渡りの短い刃物でも、頚椎あたりを切断してゾンビを即死させることができるだろう。また、即死させないまでも頚動脈を切断すれば次にそこを通るときには絶命しているはずだ。それだけでも捜索は楽になる。
手塚は手術室にあったメスのうち最も大型で、切れ味の良さそうなものを数本選び、そのうち2本を両手に構え、残りをケースに入れて持ち出した。
さて、これでこちら側のブロックはすべて見たので、もう一つの一般人立ち入り禁止のブロックに入ることにする。しかし、さすがに立ち入り禁止と言っているだけあって、そこへつながるドアには、電子ロックが掛けられていた。そして、その傍には1〜9までのプッシュボタンとカードリーダーがある。説明書きを見れば、霊安室で拾ったIDカードとパスワードの入力でロックは解除できるらしい。IDカードは問題ないとして、問題はパスワードだが…。
どうやらこのパスワード、個人を特定するためのものでなく、単にこのドアのロックを解除するためのものらしい。しかも、説明書きをよく見れば「3桁の」とご丁寧に桁数まで特定してある。こうなれば、あとは9の3乗で729通りの数字を打ち込めばいいのだが、出来ればそんな時間のかかることはしたくない。
手塚は瞬時に「手垢」を見ることを思いついた。人の手が頻繁に触れる場所には必ず手垢が付着する。
正面からは見えにくくとも、浅い角度から光を当てて見れば…。
…ビンゴ。携帯電話の待機画面を懐中電灯代わりにして横から照らすと、9つのボタンのうち3つの上にだけ薄茶色い層が見える。この時点で考えられる数字の組み合わせは3の階乗で6通りなのだが、それすらも必要なさそうだ。それぞれのボタンに付着した手垢の量からそれらのボタンが押された順番が推察できる。
しかし、よく考えれば仮にも医療に従事する人間の手指が、このように手垢が付くほど汚れていてもよいものだろうか。しかも、それが目視できるほどの期間ほうっておく清掃体制も疑問である。
ともあれ、要求された数列を入力すると小気味良い電子音と共にロックが解除され、自動ドアが開いた。その先はなぜか電気がついておらず、長く暗い廊下が伸びる。ここから先は言わば、外界から隔離された空間だ。現在、鹿尾町全体は巨大な密室であり、今までもそうだったが、これ以降は今までにまして、何が起こるか、何が現れるか、そして何に襲われるか分からない。覚悟だけはしておこう。何があっても、何を犠牲にしても生き残る覚悟を…。
廊下が真っ暗なままでは、何かと都合が悪いので、電灯のスイッチを探す。それはすぐに見つかり、切り替えてみるのだが、カチカチという音以外には全く反応が無い。…通電していないのだろうか。まぁ、後ろから差し込む光があるので当面は問題ないだろう。
その光を頼りに進むと「会議室」と書かれたプレートがあった。無論、その下にはドアがある。そのドアを注意深く開いた先に見えたのは、暗闇の中を怪しく光り、揺らめく二つの白い玉だった。部屋の中はほとんど真っ暗と言って良い状況だったが、それがゾンビとは違う、何らかの生物の双眸であることは一瞬でわかった。
だが、その思考処理のために要した一瞬が命取りになる。その生物は手塚を確認すると同時に奇声を上げながら高く跳び上がり、襲いかかった。その跳躍力は凄まじく、無助走で人の背丈に近い高さを跳び、2,3メートルはあったであろう距離をゼロにする。無論、懐にある拳銃を取り出し、構えるような余裕はない。
しかし、そのとき手塚の右手に先ほど手に入れたメスが握られていたのは幸いだった。
初動は一瞬遅れたものの、体を左前方に避ける。未知の生物の左手は、一瞬前まで手塚の頭部があった空間をなぎ払う。交差する二つの肉体。だが、手塚はその好機を逃さない。彼の右手のあったメスの刃はその生物の皮膚の上を流れていた。その手にはヌルッとした嫌な感覚、その耳には聞いたことも無い叫び声が流れ込んだ。
暗がりだったこともあり、手塚の体は勢い余ってそこにあった長机に激突する。アバラをしたたかに打ち付け、転倒しまった。だが、ダメージは向こうのほうが大きいはず。しばらくは痛みでこちらに襲い掛かってくることはあるまい。そう思った瞬間、手塚は仰向けに押さえ込まれた。彼の目の前には大きな口を開けて、あたかも笑っているかのような表情をしたバケモノがいた。粘性の高い唾液が彼の顔にしたたり落ちてくる。
人間では考えられない力だった。
絶体絶命。一体、今日何度目だろう。一応それらはすべて乗り越えてきた。だから今、自分は生きている。しかし、今回ばかりは、状況が悪すぎる。バケモノは舌なめずりをし、すでに鋭くとがった牙を剥いている。いつその歯を首筋に立てられても不思議はない。…コロサレル。
そう思った瞬間から時間の流れが遅くなり、すべての映像はモノクロになった。
…感覚が先走りする世界。
…そうだ、たった今、決意したばかりじゃないか。何があっても、生きて帰ると…。何か…、何か手があるはずだ。
自分でも信じられないほどの感覚の鋭敏さと精神の冷静さで、再度バケモノを観察し、状況を確認する。自分から見て右、バケモノの左肩から腹部にかけて、出血を伴う長く深い傷。…右腕を押さえつける力はそれほど強くない?自分がさっき、メスで切りつけたから?…ならば!