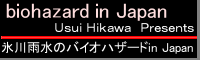第39話:損得勘定
「・・・解った。他にも色々聞きたいことはあったんだけどな。お前の話を聞いて、もうその気も失せた・・・。しかし、もうひとつだけ、これは聞いておかねばなるまい。・・・もし、『嫌だ』と言ったらどうなる?」一応聞いてみたものの、大体の予想はつく。どうせ、話を受ければ、俺の身柄と引き換えに全員無事、そうでなければ、この場で俺と樋口を殺し、その後、俺の関係者全員を始末する、といったところだろう。こういう取引では、それが常だ。だが・・・。
「言うことを聞いてくれれば、アンタのとりあえずの身の安全は確保するよ。そうでなければ、ここにいる人間は俺を含めて全員爆死してもらうことになる。」
・・・これだ。本当に最悪の状況の時、自分が、最悪の状況を想定しても事実はその斜め上を行く・・・。
「だってそれが一番安心だろ?アンタの反射神経とか、案外侮れないからさ、もしかしたら振り向きざまに、俺が引き金を引く前に反撃できたりするかもしれないだろ?だから、実はちょっとした起爆スイッチを持っててさ。まぁ、これを押すと、5分後にこの部屋と下の地下ドーム、それと、実はそっち側のはしごを上るとある建物に通じてて、そこを一気に大爆発できるってものなんだけど、これだったら撃たれても何とか押せるからね。」
確かに彼の言うとおり、いざとなれば運に天を任せて、振り向きざまに一発撃って攻勢に出るつもりでいた。これでまた選択肢が一つ消えたか・・・。
「しかし、いいのか?そんなことをしても自分が死んだら意味が無いんじゃないのか?」
彼の行動の不可解な点である。一応揺さぶりの意味も込めて言ってみたが・・・。
「別に構わないよ。どうせ、アンタを引き入れなければ、組織に始末されるだけだし、放って置いても長い命じゃ・・・、ゴホッ、ゴボォッ!」
わざとらしいほどのタイミングで咳き込む皆川。同時に血を吐いたような音だ。その音で反射的に振り向きそうになったが、何とか『こっちを向くな』という忠告を守ることができた。
「・・・演技か本気か知らんが、その程度で俺を引き込めると思うなよ。」
ここはあえて非情に徹する。だが、それは向こうもお見通しだ。
「短い付き合いじゃないんだ、そのくらい分かってるさ・・・。そのお前の冷静さ冷徹さも、実は優しさに裏打ちされてる物だっていうこともな。だから、俺はお前をテストしなけりゃならん。」
テスト。いやな単語だ。その言葉だけで吐き気を催す。
「できれば試験は、大学のものだけで遠慮したいがね。避けられないなら、受けて立つよ?」
「いい度胸だ。じゃあ、テストの内容を説明するぜ?今から俺は五つ数える。数え終わったら、有無を言わさず、引き金を引く。避けるも避けないも自由だ。まぁ、避けなきゃ死ぬのはアンタだし、避けたらその向こうの・・・、樋口とか言ったな、その人質さんに流れ弾が当たるだけだ。もちろん、それ以外の選択肢は認めない。それ以外のことをやっちゃったら、この起爆ボタンでみんないっしょに爆死、ってことになる、ちなみに、あんたが避けなかったからって、人質の安全は保証しないよ。」
案の定、吐き気がしてきた。普段の試験よりもよほどタチの悪い吐き気だ・・・。
「・・・そりゃまた、難しい問題だね。」
吐き気をこらえて、なんとかその台詞だけ絞り出す。
「そうか?ちゃんと損得勘定ができれば簡単な問題だと思うけどね。もっとも、それが出来るかどうかを見定めろっていうのが、上からの命令なんだけどさ。ま、それが出来なきゃ、『こっち側の世界』じゃあ生きていけないよ。しかし、考えても見なよ?避けても避けなくても、そこの人質さんはお亡くなりになるんだぜ?だったら、少なくともアンタだけでも助かる方が得ってものじゃあ無いのかい?」
そんなことは百も承知。だからと言って簡単に割り切れるものではない。
「それさえ出来れば、アンタ、優秀なエージェントになれるだろうけどねぇ・・・。まぁ、いいや。カウントダウンを始めるぜ・・・。はい、5ォ!」
これでもう時間は稼げない。何とかして、カウントが尽きる前に『名案』を考えつく必要がある。
「4!」
いっそ彼を見殺しにして、エージェントとやらにでもなってしまうか?向こうは随分と自分のことを気に入ってくれているみたいだし、それなりの待遇は期待できるだろう。正直、そういう世界は嫌いじゃない・・・。
「3!」
・・・いやいや、何を考えているんだ?!そんなことできるわけないじゃないか!大体、現実は映画や漫画みたいに甘くないぞ!一生太陽の光をまともに浴びられない生活など、出来るはずがないじゃないか!
「2!」
「なぁ、ちょっと待てよ!時間をくれって!そんなこと、今すぐ判断できるわけないだろ!」
畜生、考えがまとまらねぇ!
「やかましい!黙れ!それを判断しろって言ってるんだよ!ラスト、1!!」
もういい!どうにでもなるがいい!
結局手塚の下した判断、それは「判断しない」という判断だった。おそらくこのままでは二人とも共倒れだろう。それでも、彼には割り切ることは出来なかった。
「残念・・・、時間切れだ。」
未だに微動だにしない手塚を見て、皆川が言う。
「いくぜ・・・、ゼ・・・。」
『ゼロ!』のあとに聞こえるはずの銃声と、銃弾が自分の心臓を貫く感覚は伝わってこない。その代わりに聞こえてきたのは、皆川の血とともに絞り出す絶叫だった。駆け引きでもブラフでも、まして、演技でも茶番でもないことくらいは分かる。このときばかりは手塚も瞬時に振り向いた。
「な・・・!」
皆川の体は宙に浮いていた。いつの間にか背後の自分が上ってきた穴から現れた、無数の触手によって、全身を貫かれ、そして締め上げられてその体を宙空に張り付けにされていた。
『G』・・・、あそこまでして、なお生きるか・・・!
手塚の弾丸が火を噴く。それに呼応して、いくつかの触手が弾けてちぎれ飛ぶ。しかし、多勢に無勢、触手の数はあまりにも多すぎた。そして一瞬。絶望と静寂だけを残し、皆川は触手と共に暗い穴の底へと消えた・・・。しかし、認めたくは無いが、これはチャンスだ。過程はどうあれ一つの危機的状況を脱した。
「樋口、逃げるぞ!」
メスで彼を縛る縄と猿ぐつわを切り裂く。
「プハァッ・・・!でも、彼は・・・?」
「気にするな!悪役に相応しい最期を迎えただけだ!」
彼らの背後には、穴の底で事を済ませたのだろう、触手の群れが迫っていた。はしごを上るときは、体重の軽い者から。そういう原則はあるものの、手塚はあえて樋口を先に上らせた。彼には、なんとしても触手を殲滅するという役割があったからだ。この触手が健在な状態でははしごを上ることなど出来るはずもない。上っている最中に背後から貫かれるか、絡み付かれて引きずり下ろされるのがオチだ。
「うおおおぉぉぉ!」
迫る無数の触手をショットガンで吹き飛ばし、巻きついてくるものはメスで切り裂く。触手がその活動を停止するのが先か、弾、あるいは体力が尽きるのが先か・・・。ショットガンの弾が切れかけるころ、触手はようやくその動きと数を失った。これならいける。そう判断した手塚ははしごに手を掛ける。
体が予想以上に重い。しかしそれは触手が巻きついているわけでも、まして実際に質量が増加しているわけでもなく、全身に蓄積した疲労がそうさせているだけだ。その体を何とか上に引き上げる。地球の重力が恨めしく思える瞬間だ。あと数段で出口。不意に振り向いた手塚の視界にあるものが目に入る。地下ドームへ通じる穴からあふれ出る、無数の触手を伴った無秩序な肉の塊。それが『G』の、友人達の慣れの果て・・・。
出来れば戦わずに済ませたい。そんな淡い希望も希望のまま終わるのだろうと予感しつつ、はしごを上りきる。しかし、そこも屋外ではなかった。