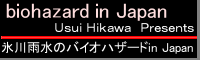第42話:終わりの始まり
これで妨害電波は消えたはずだ。付近にゾンビの姿も無い。消防署からも十分離れた。「…ちょっと、待ってくれ。今のうちに、ひとつ、済ませておきたいことがある…。」
樋口に足を止めさせ、手塚は電柱を背にして座り込み、ポケットから携帯電話を取り出した。アンテナは3本。やっと外と連絡が取れる。手塚がその指先を何度か動かすと、液晶画面上を数列が流れた…。
PRRRRR…。PRRRRR…。軽快な電子音が響く。
何をしているんだ…、さっさと出てくれ…。
明け方。小鳥もまだ目を覚まさない時刻。しかし、昼間でも薄暗いその研究室では、その暗さは真夜中と大差ない。その暗闇に電話のベルが鳴り響く。しつこく鳴り続けるベルにやっと反応するものが現れる。蠢く影。毛布の塊。その中から無精髭にまみれた男が姿を現す。一応、白衣を身に着けてはいるが、得体の知れない染みだらけで白い部分はむしろ稀有だ。
「…はい。こちら特殊病原性微生物学研究室…。」
寝起き特有ののどに絡んだような声。貴重な睡眠時間を妨げられたことによる不機嫌さにも彩られている。
「教授…。飯田橋教授ですね…。朝早く申し訳ありません…。2年の、手塚です…。」
手塚は消え入りそうな声を何とか絞り出す。
「手塚…、ああ、君か。この前の試験では悪かったね。あれはやっぱりこっちの採点ミスだ。その代わりといっては何だが、評価はAにしておいたから、まぁ、勘弁してくれ。…しかし、こんな時間に何の用だね?」
そうだった…。もとはと言えば、彼の授業で再試験を受けることになったから、こんな日に帰るハメになったんだ。もう2,3日早く帰郷していれば、ここまでの事態にはならなかったかも知れないのに…。
「事情が事情なので、用件だけ手短にお話します…。僕の故郷、鹿尾町で数千人規模の甚大なバイオハザードが発生しました…。いろいろ紆余曲折あって、原因菌と治療薬についての情報を手に入れました…。詳細は、既にメールで送られているはずです…。教授には、その治療薬を用意してもらって、、しかるべき方法を以って、この町を…、救っていただきたい…!」
この状況はそう簡単に言葉で説明できるものでは無い。それは重々承知しているのだが、一から十まで説明している暇はないし、説明したところで、理解してもらえるか、そして、信用してもらえるかすらも自信がない…。
「…?!ちょっと待ってくれ、手塚君。話が見えてこない…。一体どういうことなんだ?それに、君、大丈夫か?まるで今にも死にそうな声で…。」
だから実際、死にそうなんだって…。
「とにかく、最悪の状況をしシミュレートしてください。恐らく現実は、その斜め上を突っ走っていますから…。どんな手段でも、できれば、超法規的措置でも構いません。お願いします…、僕達を、助けてください…。」
病原性微生物学の飯田橋教授といえば、その筋では世界でも五指に入る権威らしい。そのくらいの力は持っていると信じたい。
「…分かった。君がそこまで言うんだ、相当な緊急事態なのだろう。こちらでも全力を尽くす。安心したまえ。」
「ありがとう…、ございます…。」
これでやっと、自分に出来ることは全て終わった…。手塚はそれを最後に電話を切った。携帯電話を持った左手がだらりと下がる。
「あれで、よかったんですか?」
「…何が?」
「連絡のことです。その…、手塚さんの知り合いの教授だけじゃなくって、警察とか、各種行政機関にも通報した方が…。」
警察は当てにならない。それは嫌と言うほど味わった。行政機関とやらもだ。話では、異常事態は少なくとも3日前、人間がゾンビになり始めてからですらも20時間は経っているはずだ。その間、何のアクションも無いということは、なにか裏があった事を明白にしている。仮に、正常に機能したとしても、その性格上、自分が望むような迅速な行動はとってくれまい。
「しておくに越したことは無いだろうけど…、それは君がやってくれ…。」
「…は?何故です?」
「一通りやるべきことが終わったら、気が抜けてね…。全身に力が入らないどころか…、目が…、霞んできてるんだ…。血を流しすぎたかなぁ…。」
手塚の目はかろうじて開けられているものの、焦点が全く合っておらず、その瞳にも光が無い。
「!!ちょっと、手塚さん!」
樋口は手塚の肩を掴んで、2度3度揺らす。だが、彼の身体はその動きにあわせてガクガクと揺さぶられるだけだ。気が付けば彼が腰を下ろしているその場所には、いつの間にか血だまりが出来ていた。
「俺のことはとりあえずいいから…、急いで俺の家まで行ったほうがいい…。すぐそこに見えるだろ…?みんないるはずだ…。そこまで行けば…、何とかしてくれるだろう…。」
血だまりは見る見る広がっていく。それに反比例するように手塚の声はか細くなっていく。
「そんな!自分一人だけ助かろうなんて!」
「僕だって…自分独りで死ぬつもりは無いよ…。だからさっさと行って、助けを呼んできて欲しいんだ…。一緒に行くって言ったって…、意識の無い人間は…、重いよ…?」
手塚はそれ以上、口を聞くことは無かった。
薄れゆく意識の中で、腰に付けたトランシーバーが何か言っているのが聞こえた。
「手塚先輩!やりましたね!杉田です!妨害電波がなくなったのを確認して、今、桜庭さんが例の特効薬のファイルをメールで飯田橋教授に送りました!…あれ?手塚先輩?どうしたんですか?何か言ってくださいよ?」
もう、動くことの出来ない手塚に替わって、樋口が取る。その声はもはや涙声だ。
「杉田か…。頼むから、今すぐ来てくれ。手塚さんが、大変なんだ…。」
そこまで聞いて、意識は完全に途切れた…。
真っ暗な研究室。そこにパソコンの画面だけがぼんやり光っていた。
「手塚君…。せっかく特効薬『princekiss』の合成法を送ってもらったんだが、これの合成には、いささか時間がかかるんだ…。」
パソコンの画面を覗き込んでいるのは飯田橋教授。先ほどまでの眠たそうな表情は消えている。
「しかし、君の努力に免じて、依頼は引き受けよう。結果の出ない努力は哀しすぎるからな…。まったく、私の思ったとおり優秀だよ、君は。わざわざ、採点結果に細工をして、帰郷を遅らせた甲斐もあったと言うものだ…。」
そう言って彼は受話器を持ち上げた。彼を含めて、ごく限られた人間しか知らないその電話番号は、ある場所に繋がっていた。
「はい、こちらアンブレラ特殊部隊極東総司令部…。」
「私だ、飯田橋だ。鹿尾町の作戦の件で話がある。」
凄味のある高圧的な声。それだけで彼がそれ相応の人物であることが推察できる。
「え?ああ、大方は順調ですよ。役立たずは始末したし、データも十分取れました。少しばかりうるさいガキどもがウロチョロ動いていたようですが、今から部隊を派遣して始末した上、証拠隠滅します。」
うるさいガキ…、飯田橋にはそれが手塚であることはすぐに分かった。
「ダメだ。彼らに指一本触れるな。その代わりに『princekiss』を持たせた医師団を派遣して、生き残りを片っぱしから治療させろ。」
「は?何言ってるんですか?そいつら生かしといたら、後で何をするか…。それに、わざわざ実験体を治療するなんて、非常識です。」
彼らが生きる裏の世界。表側ではありえない常識が飛び交う世界。
「構わん。この話を断ったら、今後一切の協力は停止すると思え。」
電話の向こうがにわかにざわついた…。
…白い闇。優しく暖かい底無しの沼。出来ることなら、永遠に沈み続けたかった。手塚が存在するそこは、少なくとも地獄では無さそうだった…。だが、覚醒した意識は彼が深遠に向かうことを許さなかった。目覚めてしまっては、起きなくてはなるまい。まるで気だるい日曜の朝のように…。
重いまぶたを静かに開ける。差し込む光は決して強いものではなかったが、それでも今の彼には刺激が強すぎた。
「手塚さん…。」
傍らには樋口が座っていた。ここは野山中央病院。手塚が搬送され、入院している病院だ。
「ここは…、一体…。」
体を起こそうとするとあちこちに痛みが走った。思わず呻き声を上げる。
「まだ無理ですよ、手塚さん。命を取り留めたとは言え、まだとても動ける体じゃないんです。」
改めて自分の体を見てみる。ベッドに横たえられたその体には、包帯やギプスが拘束具のようにまとわりついていた。
そして、それらが隠している傷と、その傷が与える痛みが、彼に戦慄の夜を思い出させた…。
![]()
![]()