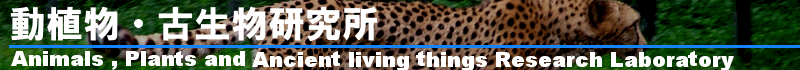続・命名の話〜シノニムって何ぞ!?
馬藤です。前回の記事が、ちょっとわかりにくかったみたいなので(すみません)再説明。なお、動物の命名規約の話なので、化石のことばかり話すにもかかわらず動物一般として書きます。
シノニムってなんぞや!?
シノニムとは、同じ種に別々の種名がついている状態を指します。
例えば、次のことを想像してみてください。
ケース1:ディプロドクス・カーネギーがまだ発見されていない時、その頭の化石と尻尾の先の化石がまったく違う場所から産出した
・・・発見した人は、それが同じ種の化石と思うでしょうか?別々の種類と考えてしまわないでしょうか?そして、それぞれに別の種名をつけてしまわないでしょうか?
あるいはこんな例はどうでしょう?
ケース2:とさかのある恐竜ランベオサウルスは、とさかの形はオスとメスの違いとされています。しかし、とさかばかりに注目した研究者はどうするでしょうか?
・・・とさかの形が違うために別々の種にわけてしまうでしょう!
こうして、同じ種に2つ(あるいはもっと)種名が付いてしまうわけです。(前の原稿で説明したとおり、交配させて確認なんてできませんからね)。この状態がシノニムです。そして研究により、それらが同じ種だとわかった場合、その余分な種名は「シノニムだった」となるわけです。なおその場合、「一番初めについた名前」が残ることになります。
また、シノニムでないか疑うということは、その種が本当は別の種と同じでないかと疑うことと同義となります。
有名な例として、昔NHKでやっていた「生命 40億年はるかな旅」で紹介されたアノマロカリスの例があります。この化石は、別々の部位が別々の種類として記載されてしまったものです。化石が不完全だったため、触角をエビ、口をクラゲ、体をナマコと思ったとか。で、化石をよくクリーニングしたらあらびっくりみんな1つでした。
この時は、一番はじめに名前のついたエビの名前が残り「奇妙なエビ」をさすアノマロカリスの名が残りました。・・・クラゲの名前が残んなくて良かったよかった・・・。
(執筆:馬藤永徳)