カメラについて語ってみる(12) 特殊なレンズについて語ってみる
ボクの住む京都では、最近、秋らしい、良い天気が続いています。読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋と、いろいろな秋がありますが、ボクは『食欲の秋』で、また、ウェスト周りを気にしなければならない、今日この頃です(笑)。
さて、今回は、ちょっと特殊なレンズについて、少し話してみようと思います。
特殊と言っても、透視ができるとか、そういったことは無いので、先に断わっておきます(笑)。この場合特殊と言うのは、魚眼レンズに代表されるようなものです。
通常の撮影用レンズは、カメラに取り付けると、
撮影倍率(=フィルム上にどのくらいの大きさで写しこむことができるか)の違いはありますが、基本的には見たままの像を写すことができます。これは、周辺に行くほど歪みの生じる現象を、レンズを組み合わせることで補正しているからです。
魚眼レンズは、この補正をしていないレンズなのです。そのため、上下左右、180度の像を写しこむことができます。
魚眼レンズにも種類があって、全周(円像)魚眼レンズと呼ばれる、天体天頂角、方位角、日照時間、輝度分布測定などの学術用途に開発されたレンズと、対角線方向に180度の画角を持つ対角線魚眼レンズがあります。
後者のほうが一般撮影向きで、現在国内で販売されている魚眼レンズも、SIGMAの全周魚眼レンズを除いて、すべて対角線魚眼レンズです。最近は、ロシア(旧ソ連といったほうが正確ですが、一般的にはロシア)製のカメラやレンズが最近流行っていますので、ロシア製の
MC
PELENG 8mm/f3.5という全周魚眼レンズを手に入れることも簡単です。

MF全盛期には、各メーカーも、全周魚眼レンズをラインナップしていたのですが、いつの間にか姿を消してしまいました。
ボクも、手持ちのレンズの中では唯一1本、魚眼レンズを持っているのですが、
MAMIYA RB67という中判カメラ用なので、重く(実測値1,480g)使いづらいです。
ですが、フィルムサイズが大きいので、魚眼レンズでうまく撮れれば面白いですよ。
左の写真は、対角線魚眼レンズで撮影したものです。被写体が大きく歪んでいます。スナップやモデル撮影で使っても面白いレンズです。

あまり、特殊レンズというイメージはないのですが、一応分類上特殊に含んでしまいます。撮影倍率1/2倍〜等倍以上の接写ができるレンズのことを指します。最近のズームレンズにはマクロ機能と言う物がついていて、1/4倍〜1/2倍くらいまでの拡大撮影ができるものもありますが、本格的な接写になると、マクロレンズが必要になります。
左の写真は、
マクロレンズによるものです。オオイヌノフグリですが、もともとは1cmほどの小さな花です。ボクの使っているマクロレンズはTAMRONの90mmですが、最大撮影倍率は
等倍です。
等倍とは、被写体のサイズがそのままフィルム上に写る倍率という事です。たとえば、1cmのこの花を等倍で写した場合、フィルム上に1cmの大きさで花が写っているということです。
マクロレンズは焦点距離50mm前後の標準マクロと、100mm前後の中望遠マクロ、200mm前後の望遠マクロがあります。一番使いやすいのは、もちろん撮影用途にもよりますが、中望遠マクロだと思います。
マクロレンズは、接写専用と言うわけではなく(中には拡大撮影用の接写専用のものもありますが)、無限遠から、かなりレベルの高い描写をしますので、ボクはこのレンズでポートレートを撮ったりもよくします。
PC(=Perspective Control)レンズとは、その名の通り、遠近感をコントロールするレンズです。
普通、ビルなどを下から見上げて撮影すると、上のほうがすぼまって写りますが、このレンズを使うと、いかにも真横から写したように見せることができます。
構造上、自動絞りができないのが難点ですが、CANONの
EOSシリーズでは、自動絞り対応のPCレンズ(CANONではTS-Eレンズと呼んでいます)がランナップされています。
これは絞り機構を完全に電子化したためにできたそうです。そのほかのメーカーのPCレンズは、ピントを合わせた後、自分で絞り込まないといけません。なかなか面倒な作業ですが、この手のレンズを使うときは三脚を使うため、あまり気にならないと思います。
ボクはNikon初期の
PC-NIKKOR35mmF3.5を使っています。
確か、世界初の35mm版PCレンズだったと思います。間違えていたらすみません。大判カメラなどでは、昔からこのような撮影(アオリ撮影と言います)が可能でした。
NikonFマウントだと、アダプターを介してCANON EFマウントに使用できるので便利です。CANONのTS-Eレンズはかなり値段が高いので、PC-NIKKORにマウントアダプターを付けておき、EOSシステムとして持ち運んでいます。とくに1vは、AEも効くのでとても便利です。
もちろんNikon用のカメラでも使えるのですが、ボクの持っているNikonカメラはNikon PhotomicFTNで、初期ニッコール露出計連動用機構が出っ張っているため、アオリ用のネジと干渉してしまいます。NikonFでこのレンズを使うためには、アイレベルファインダーを使うか、ウェストレベルファインダーを使うか、いっその事、ファインダーをはずして使わなければなりません。
すでに生産中止から30年以上たっている製品ですし、人気の高いカメラなので、ファインダーなんかも高いんですね、中古で。三脚に、Fのボディだけ付けて、RC-NIKKOR使っていれば、割とプロっぽくてカッコいいかな・・・などと不純な動機を持っていたりも(笑)。でも、1vで方眼マットスクリーンを使うのが、やっぱり一番いいんですが。
いわゆる収差を利用して、独特の滲みを出すようなレンズなどです。これについては、フィルターでも似たような効果を出せますが、厳密に観察するとソフトレンズの方が美しいですね。
ボクはほとんどこのレンズを使うことがないと考えていますので、と言うよりも、CANONに性能のいいソフトレンズがないので、買わないのですが、一応ソフトフィルターを使っています。他にはプロテクトフィルターに息を吹きかけて曇らせたり、ストッキングなどを伸ばしてレンズを覆うと同じような効果を得ることができます。
MINOLTAのソフトレンズは個人的に欲しいのですが。 MINOLTAのレンズは、結構特徴的な、個人的に好みのレンズが多いですよ。
今回は4種類、特徴的なレンズを紹介しました。このような独特のレンズは、レンズを使いこなすと言うよりも、レンズに振り回されている感じです。これが本当に使いこなせると、表現の幅が広がるのでしょうね。
さて、私事ですが、周南市美術館(山口県周南市)において、
第一回周南市美術展が行われています。合併でカウントが1に戻ったようです。そこで、私の作品も展示されています。期間は2003年10月24日(金)〜10月29日(水)です。時間があれば、見に行ってください。
それでは、気候の変わり目、体調管理には十分注意して、それぞれの『秋』を楽しんでください。

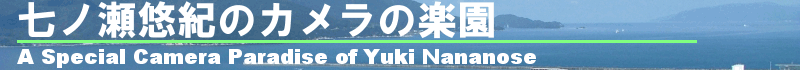
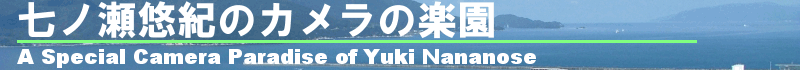
 MF全盛期には、各メーカーも、全周魚眼レンズをラインナップしていたのですが、いつの間にか姿を消してしまいました。
MF全盛期には、各メーカーも、全周魚眼レンズをラインナップしていたのですが、いつの間にか姿を消してしまいました。
 あまり、特殊レンズというイメージはないのですが、一応分類上特殊に含んでしまいます。撮影倍率1/2倍〜等倍以上の接写ができるレンズのことを指します。最近のズームレンズにはマクロ機能と言う物がついていて、1/4倍〜1/2倍くらいまでの拡大撮影ができるものもありますが、本格的な接写になると、マクロレンズが必要になります。
あまり、特殊レンズというイメージはないのですが、一応分類上特殊に含んでしまいます。撮影倍率1/2倍〜等倍以上の接写ができるレンズのことを指します。最近のズームレンズにはマクロ機能と言う物がついていて、1/4倍〜1/2倍くらいまでの拡大撮影ができるものもありますが、本格的な接写になると、マクロレンズが必要になります。