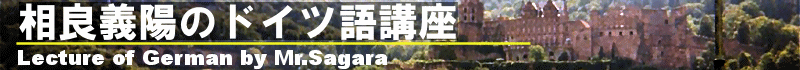
ドイツ語入門編(17) 母音交代
○母音交代の分類
ドイツ語は、母音交代が非常に多い言語です。他の言語でも、母音を変えることで意味の違いを表すことはあります(日本語でも、3「み(mi)」と6「む(mu)」、4「よ(jo)」と8「や(ja)」は、母音交代で倍数を表したのだといわれています)が、ドイツ語ほど母音交代が豊かな言語も珍しいでしょう。
当然かも知れません。そもそも母音交代が多い上に、さまざまな要因で更に母音交代が増えてきたからです。
母音交代は、以下の3種類に分かれます。
変音(Umlaut)
変音とは、アクセントのある母音が、その後にある母音 i の影響で音色を変えてしまうことをいいます。ただし、この現象の犯人であるiは、変音を起こした後で消えてしまっています。
変音は、以下の4タイプしかありません。
・a→ä
・au→äu
・o→ö
・u→ü
この変化は、主に、名詞の複数形(昔は語尾-iで作るタイプがあった)、動詞の現在形の2・3人称単数でのa→ä(e→i/ie型は後述の「折れ」という現象による)、それに形容詞の比較級・最上級、動詞の不定詞(昔-enではなく-jenで作るタイプがあったことの名残)などで見られます。
母音交代(Ablaut)
もともとインド・ヨーロッパ語族では、文法的な違いを母音を変えることで示していました。これが今になっても生き残っているのが(狭義の)母音交代です。母音交代は音韻変化の結果ではなく、意図的に母音を変えて意味の違いを表しているものですが、具体的に法則性があるわけではありませんから、丸覚えするしかありません。
ドイツ語で問題となる母音交代は、今問題になっている過去形、そして過去分詞形を作る上で生じる母音交代です。
折れ(Brechung)
ゲルマン祖語の時代に、e→i、o→uという変化が起こった際、文法変化の一部だけがi、uに変化し、残りは変化しないままだったために、ある変化形ではe,oなのが別の変化形ではi,uになるという現象です。見たところ母音交代と同じですが、起源が違います。動詞の2・3人称単数や命令形を作るときのe→i/ie型の変化がこれにあたります。
○母音交代による過去形・過去分詞形
前回は-teによる過去形、ge-...-tによる過去分詞形を扱いました。これが、いわば規則動詞で、ドイツ語では弱変化動詞と呼びます。これに対し、過去形を作るときに-teを使わず、過去分詞形を作るときにge-...-tを使わない動詞を強変化動詞と呼びます。
強変化動詞は、アクセントのある母音を別の母音に変えることで過去形・過去分詞形を作ります。
強変化動詞の過去形
強変化動詞の過去形には-teをつけません。母音が変化した時点で過去形だとわかるので必要ないわけです。
例:kommen コメン 来る
→kam-(過去基本形)
→
| 人称 | 単数 | 複数 |
| 1 | kam カム | kamen カメン |
| 2 | kamst カムスト | kamt カムト |
| 3 | kam カム | kamen カメン |
強変化動詞の過去分詞形
強変化動詞の過去分詞形には、頭にge-をつけますが、後ろには-tではなく-enをつけます。
sprechen シュプレッヒェン 話す →gesprochen ゲシュプロッヒェン
過去形か過去分詞形を作るときに母音を変化させれば、強変化動詞です。したがって、たとえ不定詞と過去分詞形の母音が同じであっても、過去形で母音の変化があれば、-enを使わなければいけません。
halten ハルテン つかむ→ gehalten ゲハルテン
kommen コメン → gekommen ゲコメン
この場合、母音は変わっていませんが、過去形がhielt, kamなので、gehaltet, gekommtではなくgehalten, gekommenになります。
○動詞の三基本形
ドイツ語では、特に動詞では、母音の交代が重要な意味を持ちます。現在形から過去形や過去分詞形を作るとき、それに現在形でも2人称単数や3人称単数にするとき、動詞の中にある母音を交代させなければならない動詞が数多くあります。しかもどの母音がどの母音に交代するのかは動詞によって様々で、決まった法則がありません。現在の2人称単数・3人称単数にするときにはa→ä、e→i、e→ieという3通りに決まっていますが、過去形や過去分詞形を作るときはそのような規則はありません。決まった法則に従わない変化を不規則変化というなら、ドイツ語の動詞のかなりの数は不規則変化ということになるでしょう。
辞書では、動詞の変化を示すために、不定詞、過去基本形、過去分詞の3つを並べることになっています。
fliegen flog geflogen (自)飛ぶ
見出し語となっているfliegenが不定詞、次のflogが過去基本形、最後のgeflogenが過去分詞形です。このように3つの基本形だけが挙げられている場合は、2人称単数や3人称単数で母音が交代することはありません。2人称単数や3人称単数で母音が変化する場合は、これも挙げます。
sprechen sprach gesprochen (現)du sprichst, er spricht (自)話す
不定詞、過去基本形、過去分詞形の母音は、
・不定詞と過去分詞が同じで、過去基本形だけが違う場合
例:geben gab gegeben (現)du gibst, er gibt 与える
・不定詞だけが違っており、過去基本形と過去分詞形が同じ場合
例:fließen floss geflossen 流れる
・不定詞も過去基本形も過去分詞形も違う場合
例:singen sang gesongen 歌う
の3パターンがあります(規則動詞、つまり不定詞=過去基本形=過去分詞形であるタイプを含むと4パターン)。
なお、分離動詞の三基本形は、過去基本形が分離した形で表示されます。過去形では常に分離しているからです。
an|nehmen nahm...an angenommen 受け取る、受け入れる
○特殊な過去形、過去分詞形
sein
seinは過去形・過去分詞形では全く別の形をしています。
sein ザィン 在る
→war-(過去基本形)
→
| 人称 | 単数 | 複数 |
| 1 | war ヴァール | waren ヴァーレン |
| 2 | warst ヴァルスト | wart ヴァルト |
| 3 | war ヴァール | waren ヴァーレン |
seinの過去分詞形はgewesenです。
haben
habenも、現在形と過去形の形が違います。但し、seinほどひどい違いが見られるわけではありません。
| 人称 | 単数 | 複数 |
| 1 | hatte ハッテ | hatten ハッテン |
| 2 | hattest ハッテスト | hattet ハッテト |
| 3 | hatte ハッテ | hatten ハッテン |
habenの過去分詞形はgehabt、つまり弱変化動詞と同じです。
stehenとgehen
stehen「立つ」とgehen「行く」も不規則な過去形・過去分詞形を持ちます。 stehen stand gestanden 立つ
gehen gang gegangen 行く
実は、ドイツ語で「不規則変化」といった場合は、強変化動詞ではなく、このような母音交代でも説明の付かない変化をいいます。
混合変化動詞
強変化と弱変化の混ざった変化をするのが、混合変化動詞です。具体的には、過去形・過去分詞形で母音を交代させるのに、-teやge-...-tという形を取る動詞です。
bringen brachte gebracht 持っていく
denken dachte gedacht 考える
kennen kannte gekannt 知っている
nennen nannte genannt 名付ける
senden sandte gesand(e)t 送る
wenden wandte gewand(e)t 裏返す、向ける など
bringenやdenkenは、歴史の中で強変化と弱変化のどちらで使われるかがなかなか一定せず、そのあげくに結局強変化と弱変化の両方の特徴を持ってしまいました。
これに対して、denken以下は、実はウムラウトによって生じたものです。つまり、本当は
kännen kannte gekannt 知っている
nännen nannte genannt 名付ける
sänden sandte gesand(e)t 送る
wänden wandte gewand(e)t 裏返す、向ける
なのですが、当のドイツ人たちが不定詞でウムラウトが起こっていることを忘れてしまったため、äではなくeで書くのが正しいということになってしまったのです。
○不規則変化動詞tun
tun「する」は不規則な変化をします。そもそも不定詞がtun、と-enで終わっていません。
現在では、-nをとって語尾をつけます。ただし1人称複数と3人称複数はtuenではなくtun。
| 人称 | 単数 | 複数 |
| 1 | tue | tun |
| 2 | tust | tut |
| 3 | tut | tun |
tunの三基本形はtun tat getanです。
さて次回。これまで過去形と過去分詞形の作り方を説明してきましたが、過去分詞形の使い方についてはほとんど説明していません。次回からは過去分詞形の使い方を説明します。まず次回は受動態。その次に完了を扱います。