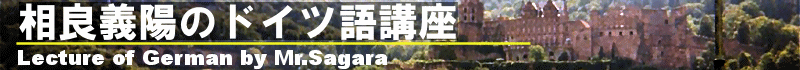
ドイツ語入門編(23) 分詞と非人称構文
○はじめに
過去分詞は一度扱いましたが、それ以外の分詞はこれまで扱ってきませんでした。それに、過去分詞に関しても、完了や受動の構文を作るときの用法だけを扱ってきて、分詞本来の使い方──つまり、形容詞として名詞を修飾するという使い方についての話は避けてきました。
分詞が形容詞として名詞を修飾するときには、文がややこしくなるから、というのがその理由です。
分詞は、英語ではparticipleなんていうわけですが、なぜparticipleというのかというと、形容詞の部分(part)と動詞の部分(part)を持っているからに他なりません。要するに、分詞は形容詞であると同時に動詞でもあるのです。つまり、形容詞として名詞を修飾する一方で、動詞として目的語やその他の副詞句を従えることが出来る、それが分詞の分詞たる所以です。
さて、話は少し変わりますが、文には締まっている部分(つまり、文法的に何かと制約のある部分)とユルい部分(つまり、制約のない部分)とがあります。どこが締まっていてどこがユルいかは言語によって違います。
例えば、日本語は、文のお尻の締まった言語です。文末には動詞が来なければいけませんし、動詞と関係の深い語はその直前に置くのが自然です。反対に文の頭はユルクて、比較的自由に語を配置することが出来ます。英語は、文の頭が締まった言語です。最初は主語、次に動詞、というのが普通であり、主語も長いといけないという制約があります。その代わり文のお尻の方はユルユルで、だらだらと語が並ぶということになることが多いものです。
ではドイツ語はどうなのかというと、頭とお尻が締まっている言語です。しかしもちろんユルい部分がないわけじゃありません。だらだらと自由に語を並べることの出来る部分がちゃんとあります。頭でもお尻でもないなら、もちろんその間です。
ドイツ語は頭とお尻が締まってその間のユルい、ソーセージのような言語なのです。外はパリパリ、中はふっくら。それがドイツ語です。
さて、頭とお尻が締まってその間がユルい、ということは、分詞と分詞にかかる目的語や前置詞句などはすべてそのユルい部分に詰め込まれる、ということでもあります。
この詰め込み方はドイツ語の特徴で、しかも慣れないと構造がどうなっているのかよくわからない、という状況を招きます。今回は分詞を扱うわけですが、問題は分詞そのものよりも分詞の作り出すこの特殊な構造の方です。今回の目的は、この構造の紹介です。また、前回、文の中での語の並べ方についてお話ししました。その並べ方に、2つ特殊事例があるので紹介することにします。第一に倒置、そして第二に非人称構文です。
○分詞
分詞とは、動詞から派生した形容詞のことです。動詞の部分と形容詞の部分を両方持っているので分詞といいます。
ドイツ語には現在分詞と過去分詞、未来分詞がありますが、過去分詞の作り方については入門編(16)で取り上げました。ここではまず現在分詞と未来分詞の作り方を挙げることにします。
現在分詞の作り方
現在分詞は、不定詞の語尾-enをとり、-endをつけて作ります。
laufen 走る → laufend
säen 種を播く → säend
sagen 言う → sagend
sein 〜である →seiend
tun 〜する → tuend
流音幹動詞、つまり不定詞が-rnか-lnで終わっている動詞の場合は、-endではなく-ndだけが付きます。
wandeln 変える、彷徨う → wandelnd
未来分詞の作り方
未来分詞は現在分詞の前にzuをつけて作ります。
laufen 走る → laufend → zu laufend
säen 種を播く → säend → zu säend
sagen 言う → sagend → zu sagend
sein 〜である →seiend → zu seiend
tun 〜する → tuend → zu tuend
○分詞の意味
現在分詞は「〜している」、過去分詞は「〜された」を意味します。これは英語と同じです。
未来分詞は「〜されうる」「〜されるべき」という意味です。
laufend 走っている、(転じて)続いている、日常的な
gesagt 言われた
zu säend 種を播かれるべき
分詞は形容詞として用いられているので、形容詞と同様に格変化をします。
laufende Nummern ラウフェンデ ヌンメルン 通し番号(直訳:続いている番号)
更に名詞化して使うことも出来ます。形容詞を名詞化して使うときは、形容詞の格変化をしたまま頭文字を大文字にします。
das Gesagte ダス ゲザークテ 今言ったこと
○名詞句の中の語の並べ方
名詞句は、冠詞と名詞のあいだにそれ以外の要素全てを詰め込むという構造をしています。
eine begrenzte Sicht
アイン ベグレンツテ ズィヒト
[begrenzen 制限する Sicht (女)視界]
限定された視界
eine auf hundert Jahre begrenzte Sicht
アイネ アウフ フンダート ヤーレ ベグレンツテ ズィヒト
百年間に限定された視界
eine auf hundert Jahre in der Geschichte eines Landes begrenzte Sicht
アイン アウフ フンダート ヤーレ イン デア ゲシヒテ アイネス ランデス ベグレンツテ ズィヒト
ある国の歴史のうちの百年間に限定された視界
このように、begrenzt「限定された」にかかる前置詞句が、begrenzteと冠詞eineの間にどんどんと挟まれていきます。結果、最初のeineがSichtにかかっているから女性形だということがわかりにくくなります。
こういった構造になるのは分詞の時だけではありません。単なる形容詞であっても、名詞句や前置詞句を取ってこういった複雑な構造を引き起こすことがあります。
der ihm ähnliche Alte wurde gefunden.
デア イーム エーンリッヒェ アルテ ヴルデ ゲフンデン
[ähnlich (3格)と同様の、に似た Alte 老人 finden fand gefunden 見つける]
彼に似た老人が発見された。
この文では、形容詞ähnlichが取った3格の名詞ihmが、derとähnlichの間に挟まっています。
○倒置
ドイツ語では、動詞以外の文成分の位置は自由ですから、倒置という概念は希薄です。ですが2つだけ指摘しておく必要があるように思います。
文末の要素を第一要素にすることも出来る
定形が助動詞であるとき、不定詞や過去分詞が文末に追いやられますが、こういった要素が文頭に来ることも可能です。
Gekommt hat dann er. ゲコムト ハット ダン エア
[dann その時]
その時やって来たのは、彼であった。
第一要素に何もなかったら、esを仮に立てる
逆に文の最初に持ってくるべき要素がないときには、esを置きます。このesに意味はありません。定形を第二位に持っていくためのものです。
Es wurde ein Alte gefunden. エス ヴルデ アイン アルテ ゲフンデン
ある老人が発見された。
以前述べたように、文頭には既知の情報をまず述べたいものです。しかし「老人」も「発見された」も未知の情報であったなら、どちらも文頭には置きたくない。というわけで、文頭には無意味なesが出現するのです。これは主語ではありません。主語はあくまでein Alteです。定形はAlteが単数だから三人称単数形になっているのです。
○非人称構文
主語が明確ではないときにも、文頭にはesが立ちます。このesは主語です。
意味上主語が必要ない文を、非人称構文といいます。「非人称」とは言いつつも、主語はesですから、動詞は三人称単数形になります。言い換えれば、非人称構文でしか使われない動詞は三人称単数形しか人称変化を持たない動詞なのです。
非人称構文を取る動詞は、以下の4タイプです。
・天候などを表す動詞
regnen「雨が降る」、schneien「雪が降る」、donnern「雷が鳴る」など。
・音や匂いなどを表す動詞
klopfen「音がする」、riechen「ニオイがする」、klingeln「ベルの鳴る音がする」など。
・感覚や心理状態などを表す動詞
感じる相手は3格で表します。また、esが文頭に来ない場合にはesを省略してもかまいません。
sein kalt「寒い」、grauen「怖い」など。
・熟語で
(6)で出てきたEs gibt (4格).で「(4格)がある」のほか、
Es geht (3格). 「(3格)の調子は〜だ」
Es handelt sich4 um (4格). 「問題は(4格)だ」、
それに自動詞の受動態Es wird (過去分詞).も非人称構文です。
さて次回。次回は不定詞句の使い方についてお話しします。