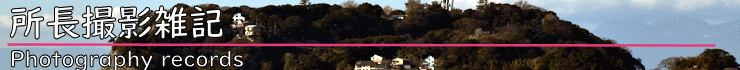2024年9月16日 東京都庭園美術館の建物公開と東京モノレール
.jpg)
この日はJR山手線の目黒駅近くにある東京都庭園美術館へ。1933年(昭和8年)5月に完成した旧朝香宮邸が前身で、外観は装飾の少ないシンプルなものですが、内装は当時流行のアール・デコ様式をふんだんに取り入れ、アンリ・ラパンやルネ・ラリックなど、様々なフランスのアーティストによる照明や壁画、レリーフなどが満載の豪華な建築で、茶室を含めて国指定重要文化財です。
.jpg)
こちらは洋館の建物背面。
.jpg)
.jpg)
茶室「光華」。1938(昭和13)年に建てられたもので、設計は武者小路千家の中村砂村(しゃそん)。施工は数寄屋建築の棟梁で名工として名高かった、平田雅哉。
.jpg)
さて、洋館部分について普段は美術館として使われているためカーテンが閉められ、少し暗い雰囲気なのですが、9月14日から11月10日まで「建物公開2024 あかり、ともるとき」として建物メインで公開され、写真撮影も可能でした。
まずは、正面玄関のガラスレリーフ。フランスのガラス工芸家、ルネ・ラリックが当館のために設計したもので、ガラスから浮き出ているような女性像が特徴です。
.jpg)
.jpg)
1階は客を迎え入れる公的な空間、2階は家族の私的な空間となっています。まずは1階から見ていきますが、こちらは大広間。アンリ・ラパンが内装設計を担当し、ウォールナット材を使用した重厚な雰囲気と、天井の格子状の中に整然と並べられた円形の照明、正面の鏡が特徴です。
.jpg)
また、フランスの彫刻家イヴァン=レオン=アレクサンドル・ブランショによる大理石のレリーフ「戯れる子供たち」がアクセントになっています。
.jpg)
.jpg)
次室。アンリ・ラパンが設計した白磁の「香水塔」や、モザイクの床が特徴です。「香水塔」は製造所の記録では「ラパンの輝く器」と記され、元々は水が流れるような仕組みだったとか。朝香宮邸では上部の照明部分に香水を施し、その熱で香りを漂わせていたことから、「香水塔」と呼ばれるようになりました。
.jpg)
.jpg)
大客室。壁面上部には、アンリ・ラパンが描く森の中の庭園の情景が描かれているほか、天井にルネ・ラリック作のシャンデリア、マックス・アングラン作のエッチング・ガラス扉とその上部にあるレイモン・シュブ作のタンパンと呼ばれる半円形部分の装飾など、部屋全体が美術工芸品です。
.jpg)
.jpg)
大食堂。来客との会食で使用した部屋で、庭園側に円形に張り出した窓が特徴。
.jpg)
照明はルネ・ラリック作。
.jpg)
.jpg)
小食堂。朝香宮家の日常の食事の場として使用されました。天井は杉の柾板(まさいた)で、やや和風のデザイン。
.jpg)
.jpg)
2階への階段
.jpg)
.jpg)
2階広間の照明。階段に設置された照明柱は詳細な資料が残っていないそうですが、ユニークな形状です。また、天井の照明は宮内省内匠寮が設計したもので、8つのランプが円形に並んでいます。
.jpg)
書庫
.jpg)
書斎
.jpg)
殿下居間。高さのあるヴォールト天井、ヒノキ材の付け柱、大理石の暖炉などが特徴です。
.jpg)
殿下寝室
.jpg)
第一浴室。殿下寝室と妃殿下寝室の間にあり、主に殿下が使用したといわれます。
.jpg)
妃殿下寝室。掲げられてている肖像画は、1924年にマニュエル兄弟が描いた朝香宮鳩彦王妃 允子(のぶこ)内親王の肖像。允子内親王は明治天皇第8皇女です。
.jpg)
ベランダ。殿下と妃殿下の居室からのみ入ることが出来、庭園が一望できます。
.jpg)
妃殿下居間
.jpg)
姫宮寝室
.jpg)
.jpg)
姫宮寝室前の照明。
.jpg)
姫宮居間
.jpg)
ウインターガーデン。朝香宮邸唯一の3階の部屋で、温室とです。市松模様に白と黒が並べられた人造大理石の床、腰壁の国産大理石が特徴です。水道の蛇口や排水溝も設けられています。
.jpg)
さて、続いて東京モノレールに乗車し、羽田空港第3ターミナル駅で撮り鉄。
.jpg)
10000形の導入により廃車が進んでいたはずの1000形ですが、3代目の標準塗装となる再リニューアル塗装も出ています。
.jpg)
主目的は、前日の9月15日に登場したばかりの10000形第4編成「開業時塗色(ラッピング)列車」。開業当初の100形を模したデザインになっており、塗装としては2003(平成15)年から2014(平成26)年まで運転された1000形第4編成(1019F)に施された100形復刻塗装以来の登場です。
.jpg)
続いて10000形第1編成による「キキ&ララ モノレール」。
.jpg)
.jpg)
四季折々のおでかけを楽しむキキ&ララが描かれています。
.jpg)
.jpg)
続いて10000形に乗車して、終点で車内を撮影。
.jpg)
さらに、羽田空港第2ターミナルで全日空などを撮影。
.jpg)
偶然ですが、特別塗装機「イーブイジェットNH」が撮影出来ました。
.jpg)
そして、第2ターミナルに新たに誕生した国際線施設3階出発ロビーで、「風神雷神図・夏秋草図屏風」の高精細複製品が展示されていました。9月30日までの展示とのことで、間近で素晴らしいものを見せていただきました。
.jpg)
.jpg)
こういうデジタルの複製品でも良いので、もっと気軽に貴重な美術品が鑑賞できるといいですね。