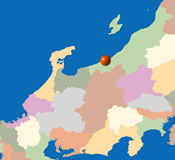
高田城と偉人ゆかりの史跡〜新潟県上越市〜
| A trip of Japan No.49 Takadacity , Niigata prefecture ( Takada Castle etc) |
| ○市の概要 |
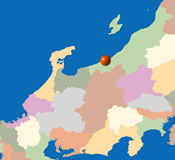 |
日本の旅 第49回 高田城と偉人ゆかりの史跡〜新潟県上越市〜
|
| 1.高田城 |
|
第47回では、上杉謙信の居城・春日山を中心にお届けしましたが、今度は高田城などを特集です。もちろん、写真は私の大先輩で、上越市出身のアンニュイアドンさん撮影。
まず最初にご紹介するのが高田城です。 1614(慶長19)年に松平忠輝の居城として築かれました。それまでの上越市には春日山城があり、城下町も、謙信の晩年には一説によると京都に次ぐ人口6万人の一大都市に発展したと言われていますが、上杉家が関ヶ原の敗戦で米沢に転封されて代わりにやってきた、当時の大名・堀秀治は、旧上杉系の人々の反乱に手を焼いたために、福島城というのを別の地に築きます。 このままでもよかったのですが、北陸・東北には前田・伊達、それからやはり上杉などという強大な外様大名たちが控えています。そこで幕府は、彼らの力を弱めるために、彼らに命じて新たに城を造らせました。陣頭指揮を執ったのは、松平忠輝の舅伊達政宗。この工事は、 関川・青田川・儀明川の流路を変えるという難しいものでしたが、着工からわずか4ヶ月で完成しています。 その特色は、石垣を用いず土塁をめぐらし、天守閣が無いこと。事実上、本丸南西の三重櫓が高田城のシンボルでした。そして廃藩置県後、高田城の建物は取り壊され、代わって軍(第13師団)が置かれます。そして戦後、意外にも最近の平成5年に、文書や古絵図、発掘調査による資料をもとに三重櫓が復元されています。 ちなみに高田藩の歴史を少し見ていきますと、まず松平忠輝は豊臣秀頼と内通しているのではないかと疑われ、さらに大阪夏の陣・冬の陣でも不祥事を起こし、兄で2代将軍の徳川秀忠によって流罪に処せられてしまいました。普通はそのまま失意のうちに病死と言ったところですが、彼は93歳まで長生きします。なんと、5代将軍徳川綱吉の治世の時まで生きたんです。もちろん、徳川家で最も長生き。かえって流罪生活がよかったのか??? で、次に来たのが松平忠昌。これはどうでもよくて、問題は息子の光長のとき。この時に後継者を巡って高田騒動が発生。徳川綱吉に睨まれ、彼自らの裁判で改易処分を受けます。この厳しい裁定は松平光長が綱吉の将軍継承に反対したため、とも言われています。その後、稲葉・戸田・松平と続き、1741(寛保元)年、榊原政永がやってくると、榊原氏のまま明治維新まで続きます。ごらんになったように、全て譜代大名ばかりで、北陸の要所として、幕府が高田を重要視していたのがよくわかります。 |
| 2.親鸞聖人と上越市 |
|
次に見ていくのが、親鸞聖人です。
親鸞は、浄土真宗の開祖として歴史の教科書にも登場する人物ですが、鎌倉幕府によって念仏停止(ちょうじ)で越後国府、すなわちこの地へやってきます。そのとき彼が上陸した地が、現在公園となっていて、親鸞聖人も見たであろう風景を見ることが出来ます(写真左)。 そして親鸞はこの地で浄土真宗を開くわけですが、その舞台となったのが浄興寺。国指定文化財でもあります。この他彼ゆかりとしては妻・恵信尼と住んだ旧跡である本願寺国府別院があげられるでしょう。 |
| 3.前島密と上越市 |
|
左写真2つは、どこで撮影したものか聞き忘れたのですが、とにかく個人的に好きな風景です。その下は、市内にある親鸞聖人の像です。
さて、写真とは全然関係ないのですが、上越市と言えば前島密(まえじまひそか 1835〜1919年)の出身地であることも忘れてはいけません。この人物は、今の日本の郵便制度の基礎を作った人で、その「郵便」という名称も彼が考案しました。 その後は、明治14年の政変によって伊藤博文らなどに政府を追い出され、その後は東京専門学校(現・早稲田大学)校長、関西鉄道社長をつとめた後、88年に本業である逓信次官に復帰。郵便だけでなく、91年には電話事業に着手、同年に退官しました。晩年は貴族院議員をつとめ、鉄道・海運事業に携わっています。 首都圏在住の方は、彼の業績について東京駅近くの逓信総合博物館で見てください。話がずれますが、ちなみにここ、昔の電話や様々な郵便ポスト、公衆電話、世界に切手などがあって結構面白いです。そして、その分館という形で上越市内に前島密記念館があります。たしか、彼の旧居跡に建っていたような・・・。 なお、前島密は「漢字なんか使うべきではない」と、幕末に徳川慶喜に建言したり、晩年まで読売新聞に投稿したりで、過激なことを言っております。理由は、数が多く形も複雑な漢字を幼少のころから学習するのは貴重な時間のむだであり、国家的損失である、とのこと。う〜ん、これだけはいただけませんねえ・・・・。漢字に変わって仮名を使えば宜しかろう、と。もちろん、これは実現しませんでしたが、その後漢字が随分と簡略化されたのは周知の通りです。 さて、記念館と言えば前回紹介した日本のスキーの父レルヒ少佐。日本スキー発祥記念館にはレルヒに関する資料をはじめ、その頃のスキー板・スキー文献など多数展示されています。 こうやってみると結構面白い上越市。この原稿を書いている私(裏辺金好)も、近いうちにぜひ訪れたいと思います・・・・。 |