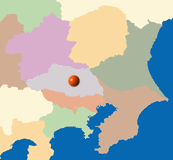
川越城と蔵造りの街並み〜埼玉県川越市〜
| A trip of Japan No.77 Kawagoe City |
| ○川越市の概要 |
埼玉県南部の都市。旧城下町を中心とした観光都市と、住宅・工業都市の両面を持ち、JR川越線、東武東上線、西武新宿線、関越自動車道と国道2本(16号、256号)が通る交通の要所。1922(大正11)年に市制施行し今に至る。面積は109.16km2。人口は約33万人。
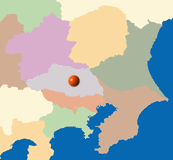 |
日本の旅 第77回 川越城と蔵造りの街並み〜埼玉県川越市〜
埼玉県南部の都市。旧城下町を中心とした観光都市と、住宅・工業都市の両面を持ち、JR川越線、東武東上線、西武新宿線、関越自動車道と国道2本(16号、256号)が通る交通の要所。1922(大正11)年に市制施行し今に至る。面積は109.16km2。人口は約33万人。
|
| 2.川越城本丸御殿 |
|
続きまして、川越城へ。と言っても、天守閣があるわけではないので、あまりメジャーではないかもしれません。
ですが、全国的にも珍しく本丸御殿が残っており、当時の藩主などの生活を知る上でも必見です。川越城の簡単な歴史を書いておきますと、ます、1457(長禄元)年、上杉持朝の命令によって、家臣の太田道真・道灌親子が築城します。 江戸時代は、江戸の北の守りとして重要視され、幕府の譜代大名達が治めます。残念ながら明治時代になって、遺構の多くが失われてしまっていますが、本丸御殿の一部が現存。1848(嘉永元)年、藩主が松平斉典の時に建てられたもので、玄関・大広間・家老詰所があります。ちなみに天守閣ですが、そもそも築かれず、富士見櫓がその代用的存在であったようですが、よく解っていません。 |
 本丸御殿(正面)
7月の暑い中の訪問でしたが、これがどっこい、内部は涼しいんです。風が上手く通ってくれて、訪問した所員一同、これが和の心か、と感心したものです(笑)。 |
 本丸御殿(側面)
|
 川越城二の丸跡(市立博物館)
蔵造りをイメージとして建築。・・・は良いのですが、せっかくなら、もう少し昔風の城郭風建物のイメージを出して欲しかった。 |
| 3.喜多院 |
|
さて、川越城と蔵造りの街並みの、だいたい中間地点に位置するのが、この喜多院。
830(天長7)年、慈覚大師が無量寿寺を開いたのがスタートで、1612(慶長17)年、徳川家康の知恵袋として有名な天海僧正が、住職となると喜多院と改めました。ところが、1638年に喜多院のほとんどが焼失してしまいます。そこで、時の将軍、徳川家光は、なんと江戸城紅葉山の客殿、書院などを移築し、未だに現存。そのため、ここには何と、「徳川家光誕生の間」、「春日局化粧の間」と伝えられる物が残り、同時に、今では櫓・門を除けば失われてしまった、江戸城の建築物の遺構となっています。 |
 喜多院山門 【重要文化財】
1632(寛永9)年築。天海僧正が造らせた物で、喜多院の中では最も古い建築物。 |
 喜多院多宝塔
1639(寛永16)年築。 |
 喜多院本殿
これは特に古くなかったはず。ちなみに、喜多院の本地堂は明治になって、上野の寛永寺に移されています。 |
|
この他、直ぐ近くの東照宮も江戸初期の建築、さらに、やはり近くの日枝神社本殿は室町末期の建築で、共に重要文化財です。撮り忘れたのが悔やまれるので、近いうちに再訪問して参ります。
|
| 4.氷川神社 |
|
川越城の北側に位置し、なんと、欽明天皇即位2年の頃(540年)の創建だと言われる由緒ある神社。
我々が訪問した時は、結婚式らしきものが執り行われており、ちと気恥ずかしかったです。 |
 氷川神社本殿
1842(天保13年)築。川越藩主・松平斉典らの寄進によって造営された物です。約5年の歳月をかけただけあって、写真では解りませんが彫刻が素晴らしいです。 |
 八坂神社本殿
1637(寛永14)年、江戸城二の丸に造られた物。1656年に川越城近くの三芳野神社に移築され、さらに1872(明治5)年に、現在の氷川神社境内に移築されました。そういうわけで、これも江戸城の遺構の1つ。 |
| 5.おまけ |
|
以上で川越の旅は終了ですが、本文中にも書きましたとおり、(あまり有名な場所ではないとは言え)貴重な建築が残る見所を見逃してしまっているようなので、また近いうちに再訪問したいと思います。さて、おまけとしまして、こんな建物。埼玉信用金庫川越西支店ですが、蔵造りの街並みに調和するように、面白い形になっています。
もっとも、街並みとは少しはずれているので要注意。メインストリートのさらにその先に行くとあります。看板に「両替商」と掲げているのが何とも素敵です。 |