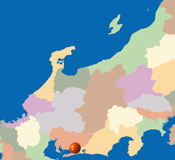| ○本陣と旅籠が残る二川宿 ところで、宿場町って何? |
JR豊橋駅から東海道本線に乗車し、僅か1駅の二川駅へ。
ここから東へ10分ほど歩くと、古い家々が点々と見え始め、そして上写真の二川宿本陣、及び東に隣接する旅籠屋「晴明屋」が見えてきます。このエリアが1601(慶長6)年、
徳川家康が東海道の集落をピックアップして伝馬朱印状を下し、宿場町として指定された場所の1つ、二川宿です。先ほどの豊橋も、江戸時代は吉田宿として栄えた場所です。
ちなみに東海道の宿場町は、1624(寛永元)年に庄野宿(三重県)が設置されて、全53の宿場町として固定されました。いわゆる
東海道五十三次です。そして、この宿場町を大名から庶民まで、参勤交代や仕事、旅行で宿泊先、休憩地点として利用したのです。
この宿場町には主に
本陣・・・大名、役人、公家の宿泊先。
脇本陣・・・本陣が満杯の場合の臨時宿泊先
旅籠屋・・・武士や一般庶民の宿泊先、食事が出てくる。
木賃宿・・・武士や一般庶民の宿泊先、食事は自炊しなければいけない。
茶屋・・・いわば喫茶店。休憩場所
といった施設が存在し、また輸送の拠点として問屋場で飛脚業務と人馬の継立(人と荷物の輸送)を行っていました。そのため、宿場町は馬100頭、人足100人を常に用意しなければならず、それでも足りない場合は
助郷(すけごう)として指定された村から、人馬を用意することになりました。まあ、これが結構な負担で・・・助郷の村で一揆が起こることがしばしばあったようです。
なお、この宿場町制度は1872(明治5)年に廃止。
人々の交通手段も鉄道へと次第に変わっていき、宿場町は衰退していきました。

二川宿本陣
現在残る二川宿本陣は、1807(文化4)年から1870(明治3)年まで本陣職を務めた馬場家の建物。現在も当時の建物が現存していますが、この本陣の建物が残っているのは東海道では二川を含めて2カ所だけとか。
|

旅籠屋「晴明屋」
本陣の直ぐ隣、左写真で言えば門の直ぐ隣の建物が旅籠屋「晴明屋」でした。平成14年に改修工事を行い、往時の姿に見事に復元されています。
|

二川宿の街並み
東海道の雰囲気をよく残す、二川宿本陣前。
|

商家「駒屋」
写真左の建物。江戸時代後期の建築。
所有者の田村家は、商家を営む一方で問屋役や名主を務めた二川宿の有力者でした。
|

二川八幡神社
二川村の氏神。1195(永仁3)年に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請されたと伝えられ、境内には、二川宿の人々が寄進した常夜灯などが残っています。
|
|
おまけとして、東海道31番目の宿場町、新井宿も少し紹介しましょう。
ここには、東海道では箱根と並び2つしかない関所の1つ、新居関所が現存しており、非常に貴重な文化財となっています。

新居関所
新居は東海道の中間に位置し、北に浜名湖、南は遠州灘という位置にあります。浜名湖対岸の舞阪宿の間に、今切渡があったため、今切関とも呼ばれました。
|

新居関所
新居関所は、現存する唯一の関所建築。1855(安政2)年に改築されたもので、1869(明治2)年に関所が廃止となった後は小学校や役場に転用され、今でも建物が残っています。関所は、江戸に入る鉄砲と、江戸に人質としておいていた大名の妻女が郷里に脱出しないよう、厳重にチェックしました。
|

旅籠屋「紀伊国屋」
新居関所近くに現存する旅籠屋。
|

新居宿本陣跡
新居関所近くにあった飯田家による新井宿本陣の跡地。現在の建物も古そうに見えますが、当時の本陣の建物は明治18年に奥山方光寺に移築されています。
|