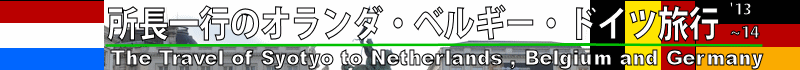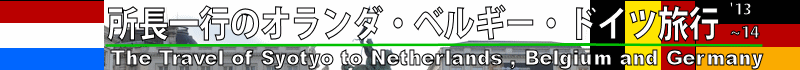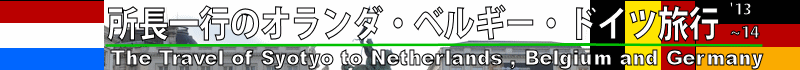
|
�S�D�A���X�e���_���F�u�A���X�e���_���������p�فv
|
|
�@����I�����_�����E�B�����P���i�P�V�V�Q�`�P�W�S�R�N�^�݈ʁF�P�W�P�T�`�S�O�N�j�̏ё���BJoseph
Paelinck �i�P�V�W�P�`�P�W�R�X�N�j���A�P�W�P�X�N�ɕ`�������̂ł��B
�@�E�B�����P���̓I�����_�i�l�[�f�������g�A�M���a���j�Ō�̑��I���j�G���E�B�����T���̑��q�ŁA�i�|���I���ɂ��I�����_�N�U�ɔ����C�M���X�ɖS���B�i�|���I�����r��A�P�W�P�T�N�ɃI�����_�����i�l�[�f�������g�A�������j���������邱�Ƃɔ����A���݂̃I�����_�A�x���M�[�A���N�Z���u���N��̗L���鍑���ƂȂ�܂����B
�@���Ȃ݂ɔނ̎������ł���P�W�R�O�N�A�x���M�[�Ŋv����������A�l�[�f�������g�A����������Ɨ����Ă��܂��B
|
|
�@���̑��q�ő�Q��I�����_�����A�E�B�����Q���i�P�V�X�Q�`�P�W�S�X�N�@�݈ʁF�P�W�S�O�`�S�X�N�j�̏ё���B�W�����E�A�_���E�N���[�[�}���i�P�W�O�S�`�U�Q�N�j�ɂ��P�W�R�X�N�̍�i�ł��B�͂��X�N�݈̍ʂł����A�]�˖��{�ɑ��A�A�w���푈��̂P�W�S�S�N�ɁA�J��������������e�̍����𑗕t���܂����A���ۂ���Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA�����̏��R�͓���ƌc�B
|
|
�@�P�W�P�X�N�ɑ���ꂽ�H��Z�b�g�B���V�A���邪�]�X�Ƃ��t�����X�œW���]�X�E�E�E�Ƃ������Ă���̂ŁA�Ƃɂ��������Ŏg��闧�h�Ȃ��̂̂悤�ł��ˁB
|
|
�@�P�W�Q�R�N�Ƀt�����V�X�R�E�f�E�S���i�P�V�S�U�`�P�W�Q�W�N�j�Ƃ����A�L���ȃX�y�C���̉�Ƃ��`����Don
Ramon Satue �Ƃ����ё���B
|
|
�@Jan Willem Pieneman�i�P�V�V�X�`�P�W�T�R�N�j�ɂ��A�u���[�e�����[�̐킢�v
�@���[�e�����[�̐킢�́A�P�W�P�T�N�U���P�W���ɃC�M���X�E�I�����_�A���R�y�уv���C�Z���R���A�t�����X�c��i�|���I��1��������t�����X�R���x���M�[�̃��[�e�����[�Ŕj�����킢�ŁA�G���o������A�҂��čc��ɕԂ�炢���A�i�|���I���ɂƂ��čŌ�̐킢�ƂȂ�܂����B
�@���Ȃ݂ɁA�����̔n�ɏ�����l�����C�M���X�̌R�l�ŁA�킢���哱��������E�F�����g�����݁E�A�[�T�[�E�E�F���Y���[�i�P�V�U�X�`�P�W�T�Q�N�j�B���ɑ��q�������]���Ă��܂��B
|
|
�@������̓���y�A�ɂȂ����s�X�g���́A���[�e�����[�̐킢�Ńi�|���I�����g�p�����i��������Ȃ��j���́B�i�|���I���̓����킢�̌�ɉ���������A���̒��ɂ����������ł��B
|
|
�@���C�E�{�i�p���g�i�P�V�V�W�`�P�W�S�U�N�j�̏ё���B�`���[���Y�E�n���[�h�E�z�b�W�X�i�P�V�U�S�`�P�W�R�V�N�j���`�������̂ł��B�Z���Ԃł����I�����_�����Ƃ��āA�Z�i�|���I���P����著�荞�܂�A�I�����_�l�̂��߂ɐs�͂��čX�R����Ă��܂����l���ł��邱�Ƃ́A�O�q���܂����B���Ȃ݂ɃI�����_�ɂƂ��ẮA���́u�����v�Ƃ������݂ł��B
|
|
�@������̓i�|���I���P���̏ё���B�W�F���[�h�j�݃t�����N�E�p�X�J���E�T�C�����iFrancois
Pascal Simon, Baron Gerard �P�V�V�O�`�P�W�R�V�N�j�ɂ��P�W�O�T�`�P�T�N�̍�i�ł��B
|
|
�@������̓��C�E�i�|���I���̊��B
|
|
�@������͂P�W�O�W�N�Ƀ��C�E�i�|���I�����p���Œ������A�A���X�e���_���Ɏ����Ă����t�H���e�s�A�m�i�s�A�m�t�H���e�j�B
|
|
�@��������͏W�c�ё���̐��E�ցB�I�����_�ł͓��ɗ��s�������̂ŁA����̐l����`���̂ł͂Ȃ��A�����̐l�����ɕ`���l���ł��B�v����ɁA�W���ʐ^�݂����Ȋ����Ŕ������āA�݂�Ȃ̋L�O�ɂ����킯�ł��ˁB���x�������`���ꂽ�l�����ŕ��S����A��l������͈����ς݂܂����B�I�����_�ŗ��s�����Ƃ����̂��~�\�ŁA�����͍��������炸�A���l�̍����������Ƃ��e�����Ă��܂��B
�@�܂��́A�o���g�����E�X�E�t�@���E�f���E�w���X�g�iBartholomeus van der Helst�@�P�U�P�R�`�V�O�N�j�ɂ��uMillitia
Company of District �[ under the Command of Captain Roelof
Bicker�v�Ƃ����P�U�S�R�N�̍�i�B
|
|
�@��������o���g�����E�X�E�t�@���E�f���E�w���X�g�iBartholomeus
van der Helst�@�P�U�P�R�`�V�O�N�j�ɂ��A�uBanquet at the Crossbowmen's Guild
in Celebration of the Treaty of Munster�v�Ƃ����P�U�S�W�N�̍�i�B
|
|
�@������́A�t�����X�E�n���X�iFrans Hals�@�P�T�W�Q���`�P�U�U�U�N�j�ƁAPieter
Codde�i�P�T�X�X�`�P�U�V�W�N�j,�ɂ��uMillitia Company of District 11 under
the Command of Captain Reynier Reael�v�A�ʏ́uThe Megre Company�v�Ƃ����P�U�R�V�N�̍�i�B
|
|
������́A�t�����X�E�n���X�iGovert Flinck�@�P�U�P�T�`�P�U�U�O�N�j�ƁAPieter
Codde�i�P�T�X�X�`�P�U�V�W�N�j,�ɂ��uMillitia Company of District �[ under
the Command of Captain Albert Bas�v�Ƃ����P�U�S�T�N�̍�i�B
|
|
�@���āA�W�c�ё���̕��͋C�͑�̉����Ă����������Ǝv���܂����A�����`�����ł���𓊂����̂��A�����u�����g�E�n�������X�E�t�@���E���C���i�P�U�O�U�`�U�X�N�j�ł����B�A���X�e���_���������p�ٓ��ł����ɗL���ȍ�i�ł���A������́u��x�iNight
Watch�j�v�Ƃ����P�U�S�Q�N�̍�i�B
�@�o��l���̑傫�����o���o���ŁA�X�|�b�g���C�g�𗁂тĂ���l��������A�������Â��`����Ă���l�����܂��B�W�c�ё���ɁA�X�Ȃ�|�p�����������킯�ł����A�������`���ꂽ�l���炷��A�u�Ȃ�ŁI�H�v�ƂȂ������Ƃł��傤�B
�@���Ȃ݂ɁA���K�ȃ^�C�g���́u�t�����X�E�o�j���O�E�R�b�N�����ƃE�B�����E�t�@���E���E�e���u���t�������̎s�����v�iDe
compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem
van Ruytenburgh�j �Ƃ��������ŁA�s�����i�Γ�e��g���ɂ��s�����x�c�j���o������u�Ԃ�`�����u���̏�i�v�ł��B�ϐF���ĈÂ��Ȃ��������ŁA��ł͂Ȃ������ł��I
|
|
�@���Ȃ݂ɂ�����A�����u�����g�炵���l�����`����Ă��邻���ł��B
|
|
�@����A�R�s�[���ʂɓW������Ă��܂��B����ׂĂ���������킩��܂����A���̕������قȂ��Ă��܂��ˁB
|
|
�@���͂P�V�P�T�N�A�Γ�e��g����z�[��������ɂ��Љ�܂����_���L��̃A���X�e���_���s�����i���E���{�j�ֈڂ��ہA�W���ꏊ�̒��ƒ��̊ԂɁu��x�v����肭����Ȃ��������߁A�㉺���E��ؒf���A���ɍ������傫������ꂽ���̂ł��B�������P�V���I�ɖ͎ʂ��`����Ă��邽�߁A�����̗l�q�����������m�邱�Ƃ��ł���Ƃ��B
|
|
�@��������u�����g�͈�ʓI�ȏW�c�ё�����`���Ă��܂��B������́A�A���X�e���_���̐D�����g���̌��{�����������iThe
Wardens of the Amsterdam Draper's Guild , Known as 'The Syndics'�Ƃ����A�P�U�U�Q�N�̍�i�B�����u�����g�̊��������̍�i�ŁA�T�l�̌��{�����������Ɩ��X�̔鏑�́A���I�ȉ�c�̏�ʂ�`���Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA������R�l�ڂ��c���B
�@�W���ꏊ�̊W�ŁA���グ�Ă��̊G�����邱�Ƃ��ӎ��������ߖ@���̗p���Ă���A���{�����������̎������A�܂�ł�����Ɩڂ����킹���悤�ȋC���ɂȂ�A�Ȃ��Ȃ��v�Z���ꂽ��i�Ȃ̂������ł��B
|
|
�@�����u�����g���P�U�Q�U�N�ɕ`����Tobit and Anna
with the Kid�Ƃ�����i�B
|
|
�@�����u�����g���P�U�Q�W�N�ɕ`�������摜�B
|
|
�@�����u�����g���P�U�R�O�N�ɕ`����Jeremiah Lamenting
the Destruction of Jerusalem�Ƃ�����i�B
|
|
�@�����u�����g���P�U�R�P�N�ɕ`����An old Woman
Reading , Probably the Prophetess Hannah�Ƃ�����i�B
|
|
�@�����u�����g���P�U�R�W�N�ɕ`����Landscape with
a Stone Bridge�Ƃ�����i�B���i��ł��ˁ`�B
|
|
�@������̓����u�����g�����q�e�B�g�D�X��`�����A�uRembrandt's
Son Titus in a Monk's Habit�v�Ƃ����P�U�U�O�N�̍�i�B
|
|
�@������̓����u�����g�̎��摜�B�P�U�U�P�N�̍�i�ł��B
|
|
�@���܂ɂ͔��p�ٓ����̗l�q���B���ɏ����Ă���̂��u��x�v�B���̑傫���A�����`���܂��ł��傤���H
|
|
�@�����u�����g�ƕ���ŕK���Ȃ̂��A���n�l�X�E�t�F�����[���i�P�U�R�Q�`�V�T�N�j�̍�i�����B�܂��A���ɗL���Ȃ�����̊G�́u�����𒍂����v�B�P�U�T�W�`�U�O�N�̍�i�ŁA�t�F�����[���̍�i�̒��ŗB��A������P�Ƃŕ`�������̂������ł��B
|
|
�@������͐߂̏��Ƃ����A�P�U�U�R�`�U�S�N���̍�i�B�����������ޗl�q�͂ق��̃t�F�����[���̍�i�Ƌ��ʂł����A�����`����Ă��Ȃ��̂������ł��B
|
|
�@�Ō�ɁA�u�����v�Ƃ����P�U�U�X�N���P�U�V�O�N���̍�i�B�莆�Ɗy��i�V�^�[���j���������ƁA������m���̏������`����Ă��܂��B
�@�w��̕ǂɊ|����C�̌i�F��`�����G�́A�����̗h�ꓮ���S���ے����Ă���ȂǁA�l�X�Ȏ����ɕx�݁A����l�̑z����~�����Ă��i�Ȃ̂������ł��B
|
|
�@���̌��e�������Ȃ�����p�j�̕������Ă���悤�Ȋ����ł����A�܂��܂��W���i�͑����܂��B������́A���C���h��ЂŊ����v�����X��E�B�������̖͌^�B�P�V���I�I�����_�ő�̖ؑ����D�ł��B
�@���Ȃ݂ɍ��͖�������I�����_�����A�P�X�W�T�N�ɃI�����_�ɔ������Ď�����ŕ����B���̌�A�I�����_�������L���Ă����n�E�X�e���{�X�̌o�c�s�U�ŃI�����_�̊�Ƃɔ��p����܂����B�Ƃ��낪�A�Q�O�O�X�N�V���R�O���ɌW����̃I�����_�k���f���w���_�[�ʼnЂ��N�����A�قڑS�Ă��Ă��܂��܂����B�d�C�n���̃V���[�g�����Ό������Ƃ��E�E�E�B
|
|
�@������͂P�U�R�T�`�S�T�N�ɋ��s�ő���ꂽ�W�t���̑傫�Ȕ��B���������G���{����Ă��܂��ˁ`�B
|
|
�@�������Hendrik van Schuylenburgh�i�P�U�Q�O�N���`�W�X�N�j���P�U�U�T�N�`�����uThe
Trading Post of the Dutch East India Company in Hooghly, Bengal�v�Ƃ�����i�B���C���h��Ђ̃x���K���n����Hooghly�ɒu�������Ջ��_�̗l�q�A�Ƃ������Ƃł����ˁB
|
|
�@������́AAndries Beeckman�i�H�`�P�U�U�S�N�j���P�U�U�P�N�ɕ`�����uThe
Castle of Batavia�v�Ƃ�����i�B�o�^���B�A �̓C���h�l�V�A�̎�s�W���J���^�̃I�����_�A���n����̖��̂ł��B
|
|
�@������͂P�T�V�T�N�`�P�U�Q�T�N���ɑ���ꂽ���{���̃g�����N�B�ł����I
|
|
�@������̓w���h���b�N�E�R���l���X�E�u���[���iHendrik
Cornelisz Vroom�^�P�T�U�U�`�P�U�S�O�N�j���P�T�X�X�N�ɕ`�����uThe Return to Amsterdam
of Second Expedition to the East Indeis�v�Ƃ�����i�BExpedition�́A�����Ƃ����Ӗ��ł��B
|
|
�@���D�͌^�R���N�V�����B�z�[���y�[�W�̃l�^�ɂȂ�Ǝv���āA�C�������ĎB�e���悤�Ƃ����Ƃ���A�ǂ̖͌^���ǂ̑D���́A�^�b�`�p�l���Œ��ׂ�����������̂ŁA���߂܂����B�^�����ւ̂��y�Y�ɂȂ�Ǝv�����̂ł����A�X�~�}�Z���E�E�E���C����������܂���ł����B
|
|
�@������͕���R���N�V�����B���͂�A�������Ȃ̂��ǂ����炸�A��������K���ɗ����܂��B
|
|
�@�P�V�O�O�N�Ƀh�C�c�̃h���X�f���ő���ꂽ�Ɛ��肳���e�B
|
|
�@�P�U���I�̍b�h�i�E�B�[�������H�j������܂����B
|
|
�@�P�U�O�O�`�Q�T�N�ɃI�����_�̃z�[�����ő���ꂽ�Γ�e�B
|
|
�@�P�U�V�O�`�X�O�N�ɓ��{�ő���ꂽ�`�E�q��̎M�B
|
|
�@���ɂ�����܂��A���M�̐��X�B
|
|
�@������͂P�V�W�S�`�P�W�O�X�N�ɃA���X�e���_���ő���ꂽ�J�b�v�ƃ\�[�T�[�i�M�j�B
|
|
�@�P�V�T�O�`�V�O�N�ɃI�����_�̃f���t�g�ő���ꂽ�M�B�f���t�g����Ƃ��Ė��������̂ŁA�I�����_���C���h��Ђ�ʂ��Ē������玥�킪�`��蓩��̐��삪���B���A����ɓ��{�̈ɖ����Ă��A���̉e���ŎQ�l�ɂ���A���W���܂����B
|
|
�@�P�V�R�T�`�T�T�N�̃f���t�g����B
|
|
�@��������f���t�g����ŁA��p���čʐF���ꂽ���̂́A�f���t�g�u���[�Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B
|
|
�@�P�V�P�O�`�Q�Q�N�ɑ���ꂽ�f���t�g����B
|
|
�@���₠�A�p��̉����p��̃z�[���y�[�W�Ƃ��ɂ�߂������Ȃ���A�W���i�̗R���ׂĂ����܂������A��ςȍ�Ƃł������܂����B���āA���̓��͎B�e������ɂďI�����A�w�O�ŐH���ɍs���܂��B
|
|
�@�X�e�[�L�n�E�X�Ə����Ă���X�����������̂ŁA�����̃l�^�̓X�e�[�L���I�Ɠˌ��B�X�e�[�L�͉��O�������ڍׂɑI�ׂ܂����A���{�̃t�@�~���[���X�g�����ƈقȂ���I�����[�B����A���C�X�Ƃ��������ɑ����z�[���V�b�N�ɂȂ�A�����B���{�̃R���Ƃ͈Ⴂ�A�p�T�p�T�ł����A���t���̓o�^�[���C�X�B���͔Z�������A���������A���ɔ������������ł��B
|
|