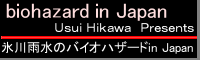第5話:閣下と呼ばれる友人
手塚の家に向かう途中、インターチェンジの前に差し掛かったとき、向こうから1台の車が走ってきた。一目でわかるGT-R。ナンバーにも見覚えがある。彼の幼なじみである皆川だ。手塚はクラクションを鳴らし、その車を止めた。「お前も帰ってきてたか…。しかし、こんな所で何やってるんだ?」
「何って…、逃げるんだよ!この町は死んだ!さっさと逃げないと、お前もゾンビに喰われるぜ!じゃあな!」
そう言って彼は思い切り後輪をホイルスピンさせ、インターに向かって急発進した。ゴムの焼ける嫌な匂いが充満する。
出来ればもっと話を聞きたかったのだが…。しかし、行ってしまったものは仕方ない。
あきらめてアクセルを回そうとした瞬間、昼と見違うような閃光と大地を揺らす爆発音が轟いた。
反射的にインターの方を見る。そこには頭のどこかで想像していた光景があった。皆川の車が爆発、炎上している。
「先輩!」
川田が情けない声を出す。
「解っている!…何か、いるな。」
そう言って、辺りに目を走らせる。
…いた。
こちらからでは背中しか見えないが、インターチェンジの屋根の上に黒いコートのようなものを着た大男が立っている。しかも、その右肩に小型のバズーカのようなものを構えて…。
黒衣の巨人は一瞬身を縮めると、凄まじい怒号と共に天を仰いだ。それは最早、声でも音でもなく空気の振動として感知される。ヘルメットがなければ、聴覚器官に失調をきたしていたかもしれない。
永遠とも思える絶叫の後、ヤツはバズーカを構えなおし、第二射を放つ。機械仕掛けの隕石はアスファルトの道路をクレーターに変える。たった一つのアドバンテージは、ヤツの注意が彼らに向いていないということだった。
チャンスは一度。今しかない。手塚は低く、小さく、しかしはっきりと言った。
「川田。」
「はい…。」
「逃げるぞ。少し飛ばす。歯を食いしばれ。」
「えっ、でも…。」
川田は割り切れなかった。彼にとっては初対面だが、手塚が友人である皆川を見捨てていくことなどないと思っていた。
「…忘れろ。あれでは…。」
車は道路もろとも原形を留めないほどに破壊されている。もはや彼も生きてはいまい。手塚は奥歯を砕けるほどに噛みしめてその場を去った。
インターホンを鳴らすと、今度はすぐに手塚の父親が出てきた。
「何だ?脱出するんじゃなかったのか?」
逃げ帰ってきたとでも思ったのだろう。彼は皮肉っぽく言った。
「そういうわけにも行かなくなってな…。彼を頼む。」
そう言って手塚は川田を前に出した。
「…よろしくお願いします。」
彼らにとってはお互いに初対面だ。さすがに困惑した表情は隠せない。
「ああ…、それは分かったが、お前はどうするんだ?」
「詳しい話は、彼から聞いてくれ。少し急ぐんだ。」
ここから一番近いのは岡崎がいるはずの沼田精肉店だ。無事ならば良いが…。 路地を抜け、ゾンビが徘徊する通りを抜け、申し訳ばかりの市街地にある沼本精肉店にたどり着く。運良くこの辺りは比較的ゾンビも少ないようだ。
「閣下!岡崎閣下!俺だ!居るんだろ!開けてくれ!」
カギは閉まっていたが、うかつに動くなといった本人だ。自分が不用意に外出などするはずもあるまい。すぐに暗闇から痩身の青年が現れた。
「おお、手塚か。何か用か?」
流石に他人に指示を出すだけのことはあって冷静だ。
「ちょっとな…。出来ればまとまって行動した方がいいと思ったんで、迎えに来た。」
岡崎はしばらく考え、そしてきっぱりと言った。
「…断る。」
予想外の返答だ。だが、ここで引き下がる手塚ではない。
「納得できんな。理由を聞かせてもらえないか。」
「…うかつに動くのは危ないからな。ここに居て助けを待った方が賢明だ。それに、爺さんと婆さんの面倒も見なくてはならん。」
「爺さん?ご主人はゾンビ化してないのか?」
「ああ…。それに。窓から外の様子はうかがっていたが、ゾンビの中に老人と子供はいなかった。まぁ、二人とも眠ってはいるがな。」
逆にいえばゾンビになったのは成人男性だけということになる。この辺りに何か秘密がありそうだが…。
手塚がそんなことを考えていると、再度岡崎から切り出した。
「とにかく、ここにいればとりあえず安全なんだ。俺は動くつもりはない。」
「安全、ねぇ…。」
手塚が重い口を開く。出来ればこんなことは言いたくなかったのだが…。
「実はな…、川田がゾンビに襲われた。亀村の家にいたにも関わらずだ。幸い、ちょうど俺がその場に鉢合わせたから良かったが…。彼を俺の家に送っていく途中で、ゾンビとは別のバケモノと遭遇してな…、今度は俺の幼馴染が殺された…。もう…安全な場所なんてないんだ…。」
気まずい沈黙。破ったのは岡崎だった。
「…一つ、聞かせてくれ。君は何のために危険を冒している?」
岡崎が神妙な表情で聞く。お互いに初めてみる顔だ。
「さぁね…。とりあえず連中を助けに行こうと思ってるが…。一つ言えるのは、安全な場所ってのは『留まるもの』じゃなくて『創るもの』だってことだ。今、この状況においてはね。」
案外戦う理由などさして重要ではないのかもしれない。敵がいる、だから戦う。それだけのことかもしれない。
「フン、クサいセリフだ…。分かったよ、俺も行こう。よろしく頼むぜ、相棒。」
「そっちこそ、随分と陳腐なセリフだな。」
お互いのセリフに二人は笑った。戦慄の夜のささやかな安堵だった…。
「さぁ、そろそろ行こう。」
一通り笑った後、岡崎が立ち上がった。そのまま外に出ようとする彼を手塚が制止する。
「慌てるなよ。アンタがうかつに動いてどうする?それより、ゾンビ共とやりあうにはそれなりの武器が必要だと思うんだが…。」
彼が最初に警官のゾンビから奪った拳銃の残弾は2発。とてもこれから起こるであろう戦闘に対応できる数ではない。
「確かに…。しかし、そんな武器なんて…。」
そこまで言って岡崎はハッとした。
「そう…。浜田銃砲店…。あそこなら最低でも狩猟用のショットガンがあるはずだ。」
「しかし、カギはどうする?窓も防弾のはずだ。」
「そこで相談なんだが…。」
こんな時の手塚の作戦はいつも強引である。
![]()
![]()