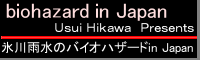第21話:不安と焦り
「えーっと、どれどれ…、『女性における第三期症状は、男性の場合と異なり、女性ホルモンに引き寄せられたウィルスは卵巣に集中、同時に自身もホルモンを放出し、排卵を誘発する。直後に卵子に寄生し、その遺伝子を組み換え…』。」文章を読み進めるに連れ、手塚の精神が掻き乱されてゆく。マウスを持つ指は震えだし、呼吸も動悸も急激に速くなる。
「お、おい、これって…。いや、こんなことが可能なのか?しかし…。」
軽い錯乱状態に陥り思考が安定しない。そんな手塚に手を差し伸べたのは狭間だった。
「書いてある内容が本当かどうかは別にして、書いてあるってことは事実なんだろう?だったら、お前がいつも言うように『最悪の事態を想定して行動する』ことが重要なんじゃないのか?」
しかし、そこに西園寺が横から口をはさむ。
「でもな、オメーは生物の専門的知識がないからそう言うけどな、常識で考えたらこんなウィルスありえんぞ。」
「あぁ?知識のこと言前も似たようなもんだろうが。大体お前は1コ下のクセにタメ口きいてんじゃねーよ!」
…。口論が始まってしまった…。無理も無い。みんな相当気が立っているんだ。
だが、西園寺が言っていることも分からないでもない。人間の卵子を変異させ、新しいB.O.W(Bio Organic Weapon、生物兵器)の胚とし、子宮内で急速に成長(その間、母体は妊娠状態になる)した後、腹を食い破って出てくるなど、そんなウィルスは確かに常識では考えられない。しかし、もう常識などという言葉は捨てたほうがいいだろう。今までの出来事も十分常識では考えられないことばかりだ。
「もう『最悪の事態』は見飽きたけどなぁ…。」
本当の『最悪の事態』など、絶対に見たくはないけれど…。手塚は今一度、腹をくくりなおすことにした。狭間と西園寺の口論は続いているが、あえて無視することにする。もう、勝手にやってくれ。
「でも、ウィルスだったら抗生物質とかで治療できないんですか?」
この藤田の何気ない一言が、後に光明をもたらすことになろうとは…。
「うーん、どうだろうな。基本的にウイルスには抗生物質は効かないし…。確かに、A型インフルエンザウイルスには、『アマンタジン』っていう抗ウイルス薬があるにはあるんだけど、あくまでもA型だけ、しかも、流行拡大を防ぐ程度にしか、効果はないんだ。とても特効薬みたいな使い方は出来ないんじゃないかな?」
なまじ中途半端な知識があると、分からなくていいことまで分かってしまい、かえって希望をなくす。
「アマンタジンかぁ…、アマンタジンねぇ…。」
桜庭が難しい顔をしてブツブツとつぶやいている。
「ん?どうした?何か気になることでもある?」
「いや、アマンタジンのスペルってこれ?だったら、どこかで見たような気がするんだけどなぁ…。」
桜庭はそのスペルである『amantadine』を画面上に打ち込み検索を掛けた。
検索は三十秒程度で終わり、全部で十数個のファイルが検出された。それらをかたっぱしから開いてみる。ほとんどは英語のファイルで、意味は断片的にしか分からないのだが。
「これだ、これだよ!俺がさっき見たのは。なんか変な単語があったから憶えてたんだ。…ほら、『prince kiss』って病院には関係なさそうじゃねぇ?」
『prince kiss』、直訳すれば『王子様の接吻』…。何のことやら…。
「王子様のキッスでお姫様の目でも覚ますんですかねぇ。」
「意外とロマンチストだな、藤田。…一応、分かるところだけ飛ばし読みしてみたが、どうやら『prince kiss』ってアマンタジンの誘導体を利用した薬らしい。合成法が説明してあるよ。」
「だったら余計に怪しいじゃないですか!『眠れる森の美女』のお姫様の名前だって
オーロラですよ!ウィルスの名前と一緒じゃないですか!」
藤田もこのウィルスに身内の者を襲われている。治療法を見つけることに関しては必死だ。もちろん手塚もそうなのだが。しかし、そうだとしたら安易すぎるネーミングセンスだ。手塚は拙い英語力で、文章を読み進める。
「…藤田君。」
「はい?」
「ビンゴだ。確かに、これは特効薬だよ…。」
「だったら!」
藤田が声を荒げる。しかし、手塚は画面を見たままで喋っている。人の目を見ず話すのは彼の特徴である。それはいいとして、治療法を見つけたというのに全く嬉しそうでないのは何故だろう。
「だが、それが分かったからといって、どうやってそれを用意する?俺だって、正確に合成法が訳せたわけじゃないし、そんな設備もここにはないかも知れん。何より、そんな悠長なことをしている時間なんてないぞ。」
…。
会話が止まってしまった。一言多かったか…。
おそらく自分の言葉が、いたずらに皆の不安を煽ってしまったのだろう。藤田にいたっては苦虫を千匹くらい噛み潰したような顔をしている。
「…まぁ、全く方法がないわけでもないけどな。」
しばらく考えた後、手塚が何か思いついたらしい。
「どうしてお前はいつもこう台詞が芝居がかってるかなぁ。」
狭間がツッコミを入れる。いつの間にか口論は終わっていたらしい。
「とりあえず、このファイルをフロッピーに焼いて。出来たら予備も含めて2,3枚くらい。で、首尾よくここから逃げれたら俺の家に行って、携帯電話で俺のノートパソコンから、うちの大学の飯田橋教授って人にメールで送りつける。電話回線は切られてるらしいからね。それで、俺が事情を説明して、教授がそれを信用してくれて、動いてくれれば万事オッケー。みんな助かりメデタシメデタシ、っていう作戦なんだが…。」
「もし…、動いてくれなかったら?」
藤田が不安そうに聞き返す。
「さぁ?手遅れになれば、僕達のお母さんはバケモノのお母さん。僕達はそのお兄さんってわけだ。君の家族も目を覚まさない。ほかにも、薬の合成法が時間のかかるものだったり、どこかから話が漏れて、お上からストップが掛かってもアウト。それより前に、フロッピーが俺の家に届かなくてもアウト。妨害電波が除去できなくてもアウト。ツッコミどころ満載、穴だらけの作戦だよ。」
あくまでも余裕綽々の表情で話を進める。その態度が藤田の癇に障ったらしい。
「よくもこんな状況で…、そんな軽口が叩けますね。家族の命が掛かってるんですよ!もっと真剣にやったらどうなんですか!」
直後に手塚の表情が深刻なものに変わる。
「…軽口でも叩いてなきゃ、やってられんさ。押し潰されそうでな…。気に障ったなら、謝るよ。悪かった。」
「あ…。」
今度は藤田が触れてはいけないものに触れてしまったような顔をした。手塚はあえてそれに気付かないふりをして、話を進める。
「さて、じゃあ、作戦行動に移ろうか。電子ロックの解除は出来てるよね?」
「あぁ…。しかし、妙なんだよ。他のロックはあっけないほど簡単に開いたんだけど、出入り口の類は異常にプロテクトが厚くて…。」
出入り口のロックが異常に頑丈…。それは『入れない』ためなのか、それとも『出さない』ためなのか…。
おそらく、後者だろう。そうでなければ自分や藤田が入れた理由が説明できない。
「まぁ、いいや。とりあえず、4階には上がれるんだよね。」
4階には院長室と理事長室の2部屋、そして、その外は屋上になっている。ここに脱出の手掛かりがあればいいが…。
みんなと別れて、独り4階へと向かう。他は引き続き、パソコンいじりだ。