| ○はじめに |
さて、早朝から小樽を見た後、午前9時30分頃にJR札幌駅へ。ここで、当研究所で考古学レポートなどを執筆されている大黒屋介左衛門さんと初顔合わせし、札幌を散策することにします。正月なので、見るべき所の大半が「お休み」という中、大黒屋さんに無理してもらって色々案内してもらいました。
| 1.たしかに凄いJR札幌駅 |
 |
 |
もっとも、当コーナーで既に何度も取り上げているような石造りの近代建築と違って安っぽさは否定できず、大黒屋さん曰く「どうせなら、帝冠様式にしてしまえば良かったのに」。帝冠様式ってのは、戦前に流行った、洋風の建築に城の天守閣みたいな屋根を取り付ける建築です。たとえば、こんなの(クリックしてください)。写真は、名古屋市役所と愛知県庁です。
| 2.定番の時計台と旧道庁 |
 |
 |
ここは、明治21年建築の、ドームを載せたアメリカンネオバロック様式の建築で、国の重要文化財。赤レンガの旧道庁という名前があまりにも有名になっていますが、現在は北海道立文書館として使用されていて、建物内は展示室となっており、北海道に関係する公文書などが展示されています。
ちなみに少し話はずれますが、この北海道立文書館のホームページに「北海道」の名前の由来が載っていまして、宜しければご覧下さい。
それから、また歩いて札幌時計台へ。札幌とと言えば定番のスポットで、観光客がよく写真を撮ります。が、ご覧のように、この建物の前の道路が狭いので、非常に撮りにくい・・・。そして、背後にあるビルが雰囲気ぶち壊し!
建物の由来は、北海道大学の前身である札幌農学校演武場として明治11(1878)年10月に建築されたもの。「少年よ大志を抱け!」で有名な、W・S・クラークの後を継いで教頭となったW・ホイラーの構想で建築された物で、なんと前後左右4つに時計があるのが特徴です(ちなみにボストン市ハワード社製)。
また、鐘は東京の工部省赤羽工作分局で造られた物、さらに時計塔正面下部の「演武場」と書かれた木額は、明治維新の元勲として名高い岩倉具視の筆による物です。現在、中では札幌農学校の歴史や、時計台に関する展示をやっています。
ん〜、くどいけど、やっぱり背後のビルが邪魔ですね。時計台の造形の美しさが、背後のビルと同化して見えづらくなっています。あと、ここで写真を撮る皆さん、絶対に家の近くにもこういった素晴らしい近代建築があるので、そっちにも目を向けてあげてくださいね(ここのコーナーを見る人は、多かれ少なかれそういうのが好きとは思いますが・・・)。
| 3.札幌市交通資料館 |
ここには、札幌市交通資料館というのがありまして、札幌市営交通の歴史を物語る貴重な写真や、かつて使用した車両や部品・制服・乗車券など展示し、実車のコントローラーとブレーキ弁で操作する模型市電などがある施設です。そして、屋外には実際に活躍していた電車やバス・地下鉄など23両が展示しています。残念ながら、開館する日は5月〜9月の日曜日・祝日・第2・4土曜日、小学校の夏休み期間中、さっぽろ雪まつり期間中と、開館日が少なく、まあ、正月なので当然ではありますが、資料館そのものに立ち入ることは出来ませんでした。
ただし、屋外展示は外から簡単に見られるので、開館日以外にここに訪れても問題ありません。いくつか御紹介しておきましょう。
 高速電車第3次試験車「はるにれ」
1965(昭和40)年製造。 |
 600形(601号)
1949(昭和24)年製造の路面電車。 |

高速電車第4次試験車「すずかけ」
1967(昭和42)年製造。 地下鉄南北線の試験に使った車両です。 |
 地下鉄南北線 1000系(1001,1002)
1970(昭和45)年製造。「はるにれ」「すずかけ」などの試験を経て、北海道で最初の地下鉄として誕生した記念すべき第1号の営業車両。ちなみに北海道の地下鉄は、ゴムタイヤの車輪という非常に特色ある車両です。 |
この他にも明治34年製、最初期の木製の札幌市電22号車をはじめ、電車や、バス、レッカー車、藻岩山のロープウェイで使われていた初期のゴンドラなどの北海道を昔走った車両が展示されています。数々の車両の展示の維持管理は大変なことと思います。ちなみに外から眺めるのはもちろん、開館日に入場しても無料です。ただ、地下鉄南北線の高架の下にあるので、ちょっと圧迫感が・・・。(地下鉄ですが、この辺は地上はおろか、その上を走っているんですね)。さて、次のページへ続きます。
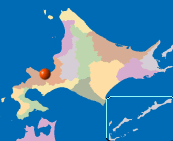 日本の旅 第66回
日本の旅 第66回